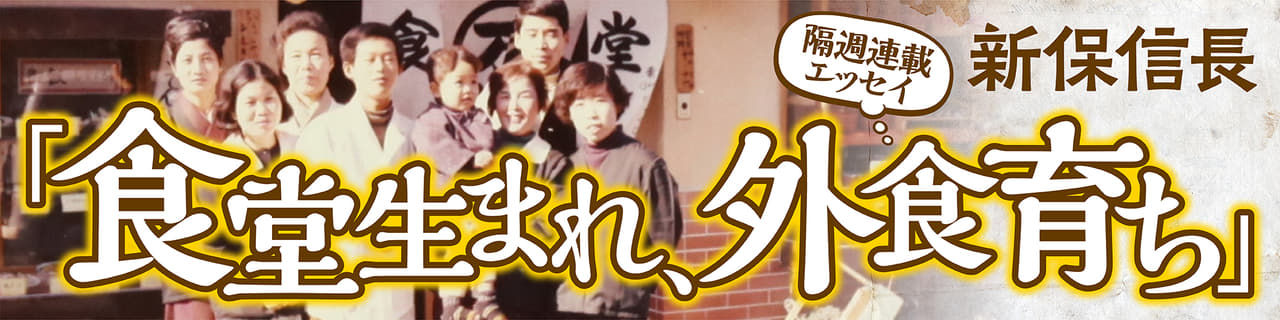新保信長『食堂生まれ、外食育ち』【2品目】外国人と鴨南蛮と中華そば
【隔週連載】新保信長「食堂生まれ、外食育ち」2品目
「食堂生まれ、外食育ち」の編集者・新保信長さんが、外食にまつわるアレコレを綴っていく連載エッセイがスタート。ただし、いわゆるグルメエッセイとは違って「味には基本的に言及しない」というのがミソ。外食ならではの出来事や人間模様について、実家の食堂の思い出も含めて語られるささやかなドラマは、あなたを「いつかあの時の〝外食〟の時空間」にタイムスリップさせてしまうかも……。それでは【2品目】「外国人と鴨南蛮と中華そば」をご賞味あれ。✴︎連載全50回がついに書籍化、絶賛発売中です!

令和の今、街で外国人を見かけることは珍しくない。東京ではコンビニのレジからしてほとんど外国人だし、飲食店でも外国人の店員は多い。アジア系だけでなく、白人も黒人も普通にそのへんを歩いている(ここ2年ほどはコロナ禍の影響で減ってはいるけれど)。地方都市でもそれは変わりないどころか、地域によっては東京より外国人比率の高い街もあると聞く。
とはいえ、私が子供の頃はまだ、大阪の中心部でも外国人はそれほど身近な存在ではなかった。焼き肉の聖地として知られる鶴橋とかに行けば韓国系の人は大勢いたのだろうが、少なくとも当時の自分にとっては未知の領域であった。
そんなある日、ウチの食堂に白人の客が来たのである。子供の目にはおっさんに見えたが、20代かせいぜい30過ぎぐらいだったかもしれない。近所に英会話学校やデザイン専門学校があったので、そこの講師か、あるいは単にどこかの会社で働いている人か。たまたま客の少ない時間帯で店をうろついていた私は、物珍しさもあって、ちらちらと様子をうかがっていた。
その白人の兄ちゃん(おっさんではなかった気がしてきた)が注文したのは、鴨南蛮。前回【1品目】で掲載したウチの食堂メニューでは「かもなんば」という表記になっている。関西では「南蛮」ではなく「なんば」と呼ぶのが一般的らしいが、そもそもなぜあの料理を「鴨南蛮」と呼ぶのか? と思って調べてみたら、江戸時代に南蛮渡来の唐辛子や南蛮人が好むネギが入った料理を「南蛮」と呼ぶようになったらしい。今となってはポリコレ的に微妙なネーミングではあるが、白人の兄ちゃんが注文するにはピッタリとも言える。
しかし、その兄ちゃんの食べ方が普通じゃなかった。まず、れんげでおつゆを全部飲む。次に、汁気がなくなったそばの上に取り残された肉とネギを食べる。そして、おもむろにテーブルに置いてあるソースを手に取ったかと思うと、ツツーッとそばにかけ始めたのだ。
私がキムタクなら「ちょ待てよ!」と言う場面である。いや、その頃キムタクは生まれてるかどうかぐらいだが、そばにソースってアンタ……。つーか、なんでおつゆを先に全部飲んじゃった? 肉、ネギ、そば、つゆの芳醇なマリアージュを味わってこその鴨南蛮でしょう。外国人はそばをすするのが苦手らしいけど、だからってその食べ方はないだろう……なんて、子供の頃の自分がそこまで考えたわけではないが、「え、何やってんの?」と目を疑ったのは事実である。が、当の兄ちゃんは、日本人の子供の視線など気にもせず、ソースをかけたそばを割りばしで器用に食べて帰っていった。
- 1
- 2
KEYWORDS:

✴︎KKベストセラーズの7月新刊✴︎
新保信長 著『食堂生まれ、外食育ち』
作家・平松洋子さん推薦!!
「気配をスッと消し、食の現場をニヤリと斬る。
選ばしし外食者の至芸がすごい。」
外食歴50年超の著者が綴る異色の外食エッセイ!
一口に「外食」と言っても、いろんなシチュエーションがある。子供の頃に親に連れていかれたデパートの大食堂。夜遅く仕事帰りに一人で入る牛丼屋。ここぞというデートや記念日に予約して行ったレストラン。気の置けない仲間と行く居酒屋。たまの贅沢のカウンターの寿司屋。出先でたまたま入った定食屋。近所のなじみの中華屋や焼き鳥屋……。
誰もが心当たりあるような懐かしくも愛しき「外食の時空間」への旅が始まる!
カバー&本文イラスト描いたイラストレーターおくやまゆかさん。
イラストが最高に愉快!(全50点収録)
目次
序 「今日のごはん何?」と聞いたことがない
第1章 ノスタルジア食堂
1品目|外国人と鴨南蛮と中華そば
2品目|ランチタイム地獄変
3品目|「天丼」と「うどん天」と「シマ」
4品目|出前とデリバリー今昔物語
5品目|おでん定食というギャンブル
6品目|ハンバーグ記念日
7品目|おいしい味噌汁の条件
8品目|最高のおやつ
9品目|校外学舎の悲しき夕食
10品目|わんこスイカ
11品目|ところ変われば品変わる
12品目|「恵方巻」と「丸かぶり」
13品目|ちくわぶとはんぺん
14品目|「肉じゃが=おふくろの味」って誰が決めた?
15品目|スマホがなかった時代
16品目|Gに気をつけろ!
第2章 私が通りすぎた店
17品目|あの素晴らしい寿司屋をもう一度
18品目|気まぐれすぎる女将
19品目|選択肢のない店
20品目|日本一大きいビアガーデン
21品目|カニ・マイ・ラブ
22品目|国会図書館でナポリタンを
23品目|夫婦の肖像
24品目|サハリンの夜
25品目|インドで大炎上
26品目|開幕前の至福の宴
27品目|私がスポーツジムに通う理由
28品目|かわいそうな寿司屋とその弟子
29品目|残業メシ格差
30品目|よそンちの食卓はつらいよ
31品目|大食いと早食い
32品目| BGMも味のうち?
第3章 外食の流儀
33品目|大盛りはうれしくない
34品目|取り皿問題
35品目|デザート嫌い
36品目|お熱いのはお好き?
37品目|器のTPO
38品目|あんまり尽くされても困る
39品目|スパゲティがパスタに変わった日
40品目|何をかけるか問題
41品目|どの席に座るか問題
42品目|酒飲み認定
43品目|11人きた!
44品目|硬と軟
45品目|人はだいたい同じものを注文する
46品目|トングどっち向きに置く?
47品目|箸と愛国
48品目|ステキなタイミング
おわりに 入れなかったあの店の話