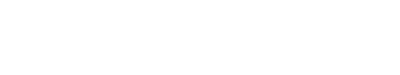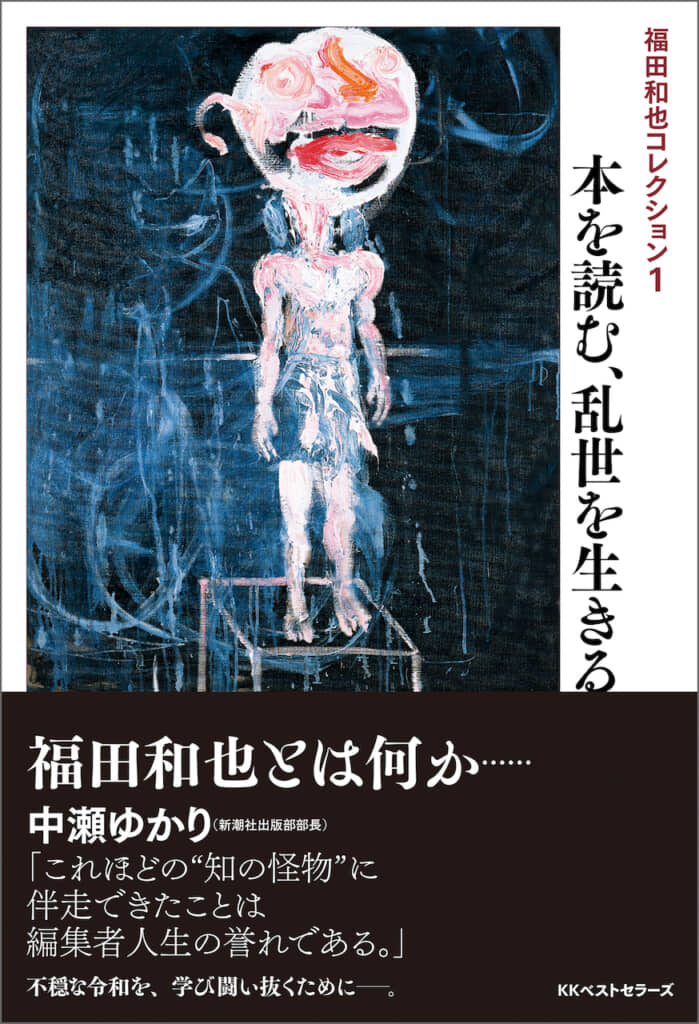不穏な時代の「価値ある読書」こそ人間を精神から鍛えなおしてくれる【福田和也】
“知の怪物”が語る「生きる感性と才覚の磨き方」
「本を読むとはどういうことか?」「もっとたくさんの本を読めるようにするにはどうしたらよいか?」そんなテーマの本が出版市場を賑わしている。多くの人が今、何か精神的な支柱を読書に求めている表れなのではないだろうか。類のない読書家であり〝知の怪物〟と評される福田和也氏の著書『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』(KKベストセラーズ)から、珠玉の読書論を抜粋。“不穏な時代を生きる感性と才覚の磨き方”とは。

■なぜ人は本を読むのか
なぜ本を読むのか。
そうした疑問を、あなたは感じたことがあるだろうか。
もしも感じたことがあり、そのことについて考えたことがあるのなら、それだけで君の人生は何ほどかのものだ。身近なことについて、根本的に考えるということはなかなか難しいものだし、さらに自分なりの答を得るのは大変に難しい。
だが、大部分の人間は、私もそうだけれども、そういった問いを持つことなく、書店で本を手に取り、頁に視線を走らせ、そして読み終わるなり飽きるなりすれば、放りだしてしまう。本とのつきあいのなかで、強い印象を受けたり、考えさせられたりはする。その印象がきわめて強いものならば、いつまでも記憶に残っていたり、人に印象を伝えたくなる。そうでなければ、何となく面白かったとか、悲しかったといった感触だけが残って、じきに忘れてしまう。ほとんどの人にとって読書とはそういう経験だろう。楽しみ、暇つぶし、あるいは多少の教養と情報収集のために、書物を手に入れ、頁を繰る。
にもかかわらず、あなたがまた書物を手にするのはなぜなのか。
楽しむためならば、情報のためならば、もっと気の利いたものがたくさんあるのに。テレビ、ビデオ、ゲーム、インターネット……本は数千年前に作られた文字と紙、それに五百年前に発明された、印刷技術という折り紙つきの旧弊なテクノロジーの産物である。
本などは、今になくなるという予測が、マスメディアに溢れているのも無理からぬことだ。にもかかわらず、あなたが本を手に取るとしたら、それはなぜなのか。
あなたが、今日の世の中では、時代遅れとしか云い様のない感性しか持っていないからなのか。
それともあなたが、書物にしかない魅力に、魅力という言葉では示しきれない力に気づいているからなのか。
何を本は提供してくれるのだろう。
その提供してくれるものを、小説にのっとって考えてみることにしようか。
それは、ドラマであり、情景であり、感情の経験だ、と云うのは正しい。そうしたあらゆる要素が入った、一つの物語的な世界に入ることだ、と云うのはもっと正しい。
けれども、それならば小説を読むということは、映画を見たり、ゲームをやったりすることと同じなのだろうか。
確かに映画も、ゲームも、一つの物語的な世界を体験させてくれる。
しかも、小説よりも、数段サービスたっぷりに。映画には具体的に映写される情景がある。光があり、影があり、人々の顔があり、姿がある。声があり、物音があり、音楽がある。さらにゲームならば、あなたはその世界自体にかかわることができる。それなのに、なぜあなたは本を読むのか。
KEYWORDS:
✴︎KKベストセラーズ 好評既刊✴︎
『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』
国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー
学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。
文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集
◆第一部「なぜ本を読むのか」
◆第二部「批評とは何か」
◆第三部「乱世を生きる」
総頁832頁の【完全保存版】
◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)
「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。
彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。
これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」