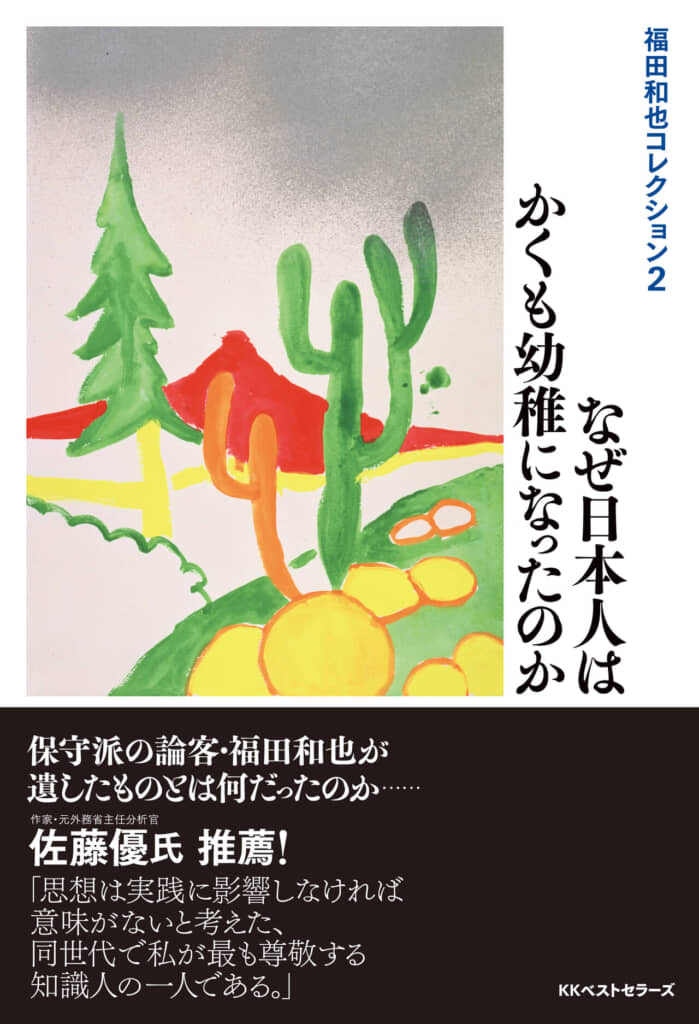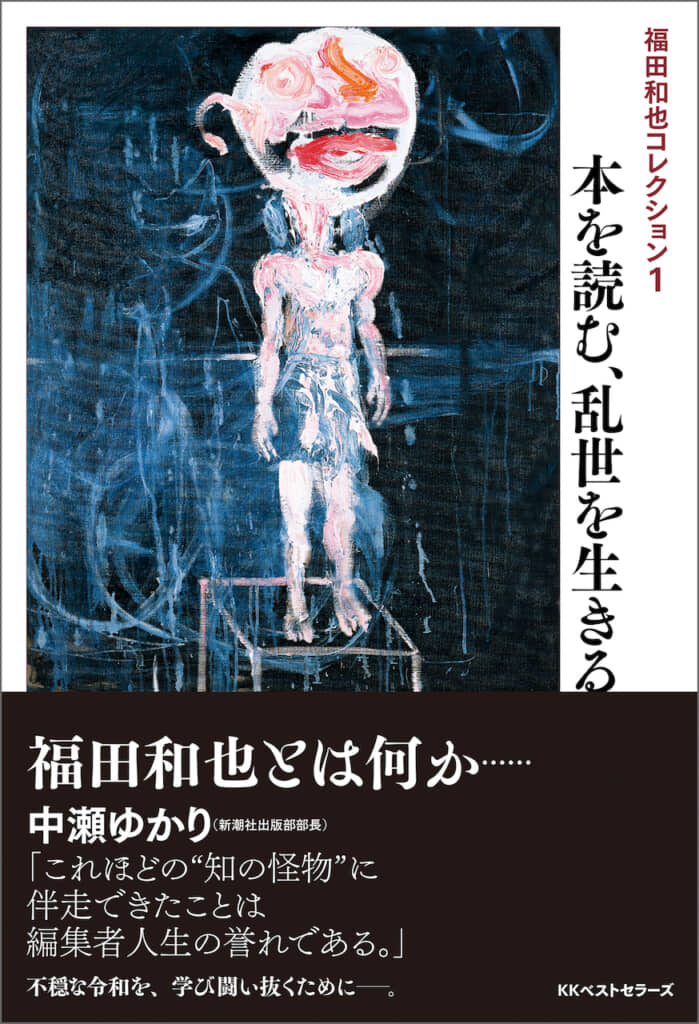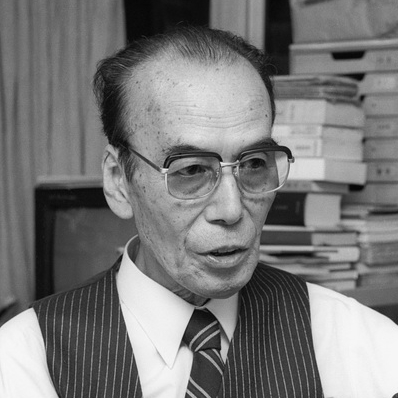見えなくなったものを忘れるな! 柴崎友香著『帰れない探偵』を読む【緒形圭子】
緒形圭子「視点が変わる読書」第22回 『帰れない探偵』柴崎友香著
■情報と富をもつ少数の特権階級と戦い続けるために
「市場において、各個人の利己的な行動の集積が社会全体の利益をもたらす」という、「神の見えざる手」を説いたのは、古典派経済学の祖、アダム・スミスだが、21世紀初頭の現在ですでに人間の欲望は「神の見えざる手」を超えてしまった。
今後世界はいよいよ、情報と富を手にしたごく少数の特権階級と彼らに支配されるしかない大多数に分かれていくことだろう。
『帰れない探偵』にはそうした世界が如実に描かれている。
わたしが滞在していたとある町では、公共交通の運賃を値上げした市長に対し、住民が大々的なデモを起こした。すると突然街の半分が停電になり、それをきっかけにデモは勢いをなくしてしまった。
探偵という職業柄、わたしはその土地土地の図書館で地図を見ることが多い。ある時、町の昔の地図を見て、違和感を覚える。はっきりどの部分とはいえないが、細部が整い過ぎている気がしたのだ。誰かに巧妙に修復されたかのように。
リゾートホテルでスパイと思しきファミリーを監視していたわたしは、逆に助手として送り込まれた産業スパイに情報を盗まれ、薬を盛られ、後遺症に苦しむことになる。
わたしの祖国では、国や行政組織の記録が改竄されたり、架空の統計が計上されてもたいしたニュースにはならなくなっていて、それを指摘した人たちのほうが、政治に混乱や停滞を招くと批難を浴びるようになっている。
こうした監視や支配が日常化される中、多くの人は問題意識を持って抗議行動を起こすことをやめ、自分たちができる範囲で生活を楽しむようになる。
庭で薔薇を育てたり、トマトと魚のスープを作ったり、お祈りを捧げたり、登山をしたり、絵を描いたり、音楽を奏でたり……。
特に音楽はこの小説では大きな役割を果たしている。
どこに行っても音楽がある。どこの街へたどり着いても、音楽があればそこに居場所がある気がする。帰る場所がなくても、音楽がある場所にはしばらくいていいのだ。音楽が続く限りは。
わたしの述懐である。音楽は人間の自由と意志と結託の象徴なのだ。
最終章の「歌い続けよう」で、わたしは世界探偵委員会連盟の指令で10年前に離れた祖国の、自分が生まれ育った街の空港に降り立つ。
そこで、わたしは偶然高校時代の同級生と会う。彼女との短い会話の中で、わたしはその日空港に隣接する人工島で行われるライブイベントの前にゲリラライブが決行されるという情報を得る。
果たしてゲリラライブは決行された。人工島の近くに碇泊した船から花火が上がり、サンバに似たリズムが流れてくる。たちまち警報音が鳴り響いたが、わたしには、ところどころ歌詞が聞き取れた。
「ここにいる」
「戦うために」
音楽が続いている間は、私たちはまだ戦うことができるのだ。
それさえできなくなってしまわないよう、私たちにできることは、見えなくなったものを忘れないことではないだろうか。
文:緒形圭子
KEYWORDS:
✴︎『福田和也コレクション』新刊発売中✴︎
『福田和也コレクション2:なぜ日本人はかくも幼稚になったのか』
福田和也 著
全国民必読!
保守派の論客・福田和也が
遺したものとは何だったのか・・・
佐藤優氏(作家・元外務省主任分析官)推薦!!
✴︎「思想は実践に影響しなければ意味がないと考えた、同世代で私が最も尊敬する知識人の一人である。」
✴︎「私は「保守派の論客」という規定では、福田氏のスケールをとらえ損ねると考えている。」
✴︎「福田氏は、保守派の論客であるが日本国家が自明であるとは考えていなかった。」
✴︎「福田氏が考えていたのは、全ての人間に備わった責任感ということだったように私には思えてならない。」
✴︎「『真剣な問に対して、責任を持って答えるとはどういうことか』について、私は福田氏から多くを学んでいる。
第一部 日本とは何か
日本の家郷
「内なる近代」の超克
日本人であるということ
乃木希典
保田與重郎と昭和の御代
第二部 ナショナリズムとは何か
なぜ日本人はかくも幼稚になったのか
この国の仇
余は如何にしてナショナリストとなりし乎
大丈夫な日本
【解説一】西部邁 【解説二】久世光彦 【解説三】角川春樹
本書解説 佐藤優
「福田和也氏の普遍主義とアナーキズム」
総頁676頁の【完全保存版】
✴︎好評既刊✴︎
『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』
国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー
学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。
文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集
◆第一部「なぜ本を読むのか」
◆第二部「批評とは何か」
◆第三部「乱世を生きる」
総頁832頁の【完全保存版】
◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)
「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。
彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。
これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」