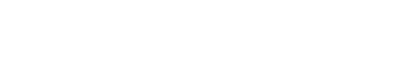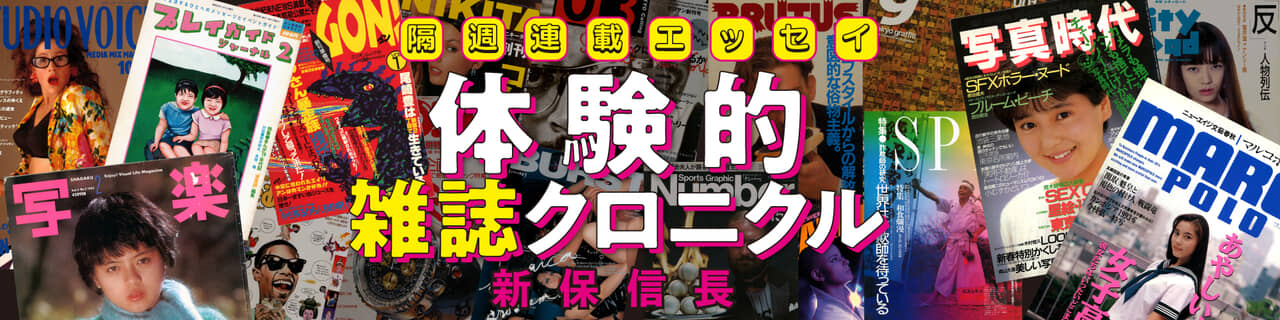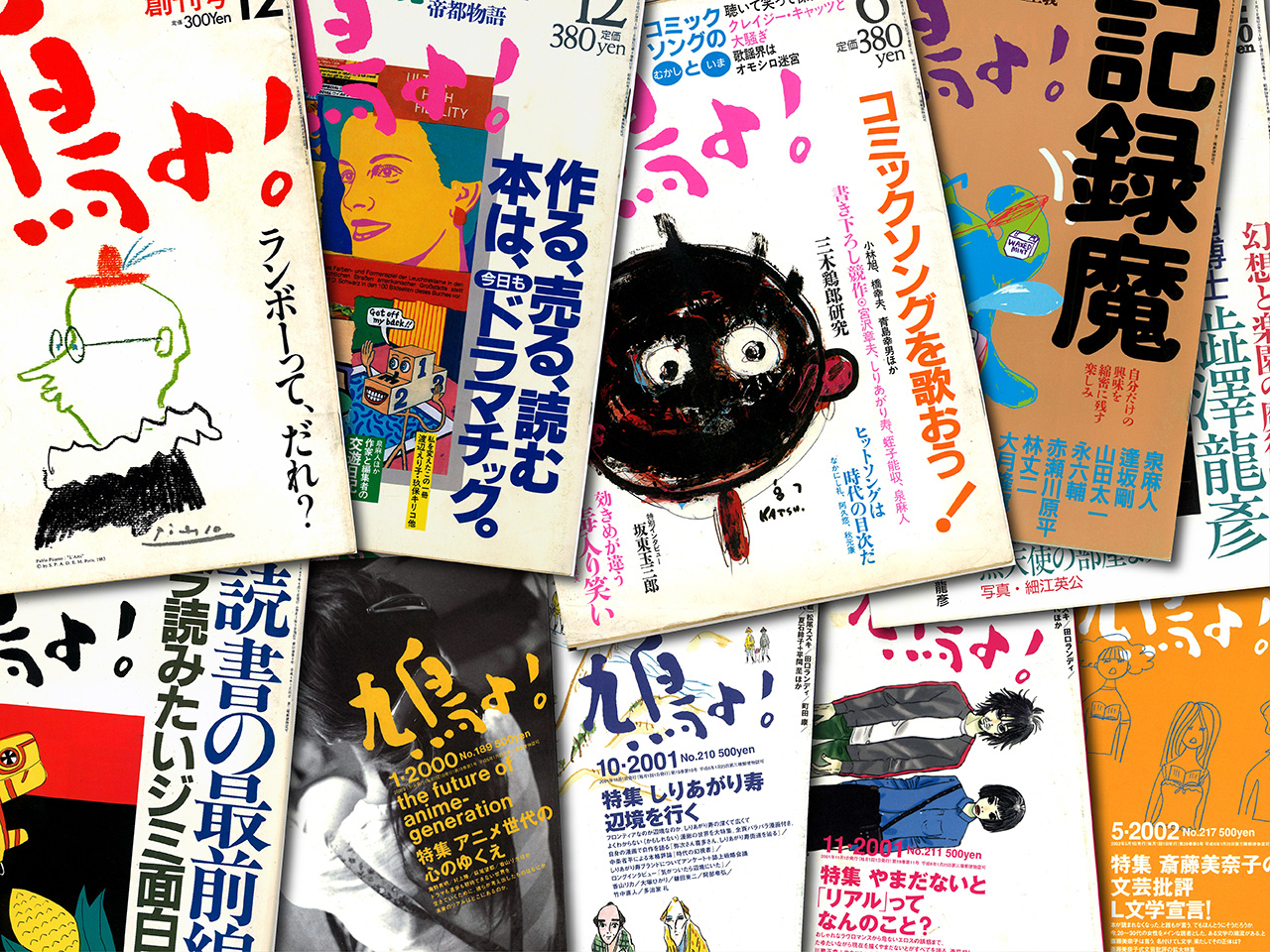『散歩の達人』の歩き方【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」16冊目
新保信長「体験的雑誌クロニクル」16冊目
3号目(6月号)の第一特集は「昭和[高度成長期]の東京を歩く」と、これまたマニアックというかレトロな切り口。昭和の団地を再現した展示のある松戸市立博物館、昭和の家電などが展示された江戸東京博物館、懐かしのおもちゃを収集展示する日本玩具資料館などを紹介したかと思えば、スピッツや伝書鳩などの昭和のペットブームを追跡し、老舗のビリヤード場や名曲喫茶を訪ね歩く。「あの名ドラマの舞台を訪ねて」では、『太陽にほえろ!』『傷だらけの天使』『俺たちの旅』といったドラマの聖地(当時はそんな言い方はなかったが)を巡礼する。
その後も「真夏の夜の東京奇談」(1996年8月号)、「街に赤線があった頃」(11月号)、「平成珍不動産事情」「山手線車窓風景の謎」(ともに1997年3月号)といったクセの強い特集が続く。「東京梅雨花散歩指南」(1996年6月号)、「東京・秋景色さがし」(11月号)なんて風流な特集や「東京御利益スポット大全」(1997年1月号)、「横浜中華街の素顔」(2月号)のように街歩き雑誌の本領発揮の特集もあるにはあるが、創刊当初の『散歩の達人』はレトロとサブカルの見本市だった。
特別企画はさらにやりたい放題で、「悶絶トイレ大研究」「この街が嫌い」あたりはまだ散歩要素があるものの、「今どきの結婚式大研究」「男芸者という生き方」「草野球バカ一代」となると散歩とまったく関係ない。かといって「散歩の新スタイル 尾行が今、密かなブーム?」というのは、いくら何でも無理があるだろう。
さすがにマニアックすぎて売れ行きが芳しくなかったらしく、創刊から約1年を経た1997年6月号で同誌はリニューアルとなる。B5判・平綴じからA4変型判・中綴じに。タイトルロゴやキャッチコピーはそのままだったが、表紙デザインは変わってメジャー感が出た(デザイナーは同じ)。特集も「散歩式GINZA案内 銀座でなごむ」と、エリアテーマのメジャー路線。王道のタウン情報誌として生まれ変わったように見える。
個人的にはマニアックなほうが好きだったので、ちょっと残念な気がしつつもとりあえずページを開いて思わず苦笑。銀座特集を謳いながら高級店は一切出てこない。路地裏にたたずむ美女の写真をどーんと使った見開き扉から、銀座の歴史、ガード下の飲み屋、老舗の個人商店、路地裏のなごみスポット、安くてうまい庶民派グルメ、銭湯やサウナ、ミニシアターなど、まさに「散歩式GINZA案内」が展開されているのだ。同じ銀座特集でも『Tokyo Walker』や『Hanako』(マガジンハウス/1988年創刊)では、こうはいくまい。

以降、「谷中・根津・千駄木」(1997年9月号)、「いざ!! 秋の鎌倉へ」(11月号)、「都電荒川線沿線」(1998年3月号)、「いくつになっても渋谷だ!」(2000年1月号)、「四谷・麹町・荒木町」(10月号)、「川崎・鶴見」(2001年6月号)、「麻布十番・広尾」(2002年9月号)など、エリア特集が増える。が、その切り口にはやはりひとひねりあり、「コマダムだってにんげんだもの」(二子玉川・用賀)、「海と川とプロレタリアン・ブルースの愉しみ」(川崎・鶴見)といったサブタイトルも気が利いてる。
メインとなるエリア特集の陰に隠れてマニアックな企画も健在で、「東京廃墟な街角巡礼」(2000年7月号)、「イカス! 自販機天国」(10月号)、「あまりにも芸術的な[固形石鹸]」(2001年5月号)、「気になる木に瞠目せよ!」(6月号)、「河童を信じるこれだけの理由」(2002年7月号)、「ちょっといい箸」(2003年2月号)など、バラエティ豊か。「河童を信じるこれだけの理由」って、何を言ってるのか。