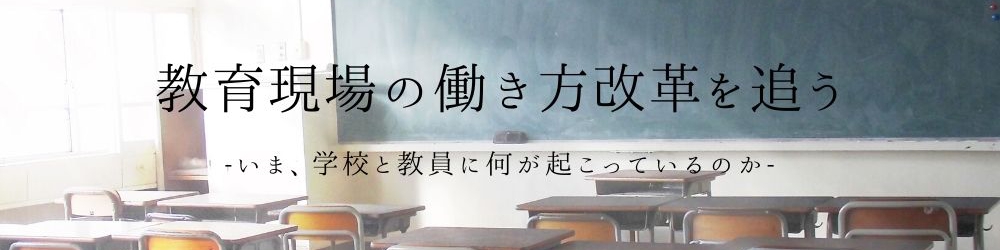【時代に合わない給特法】もはや残業代では補えない、教員の激務
第99回 学校と教員に何が起こっているのか -教育現場の働き方改革を追う-

多様性が求められる現代では、多くの変化が生まれている。しかし、なかなか変わらないものも少なくない。かつては教員を助けた「給特法」もその一つだろう。コロナ禍を経て、さらに多忙となった教員たちに今、必要なものとは何なのだろうか…。
■教員に残業代は支払われない
教員の多忙が問題視されるようになって久しいが、いっこうに改善する方向へと向かわっていない。過労死ラインを超える労働時間を強いられながら、残業しても残業代が支払われないなど、一般企業に務める労働者からは信じられないことに違いない。しかし、それが教員の実態でもある。
時事通信社のウェブ媒体『JIJI.COM』は10月2日付で、「教師の働き方改革、道半ば 残業常態化、志望者減る—文科省」というタイトルの記事を載せている。そこに「残業代の支給は難しい」という文科省幹部のコメントを紹介し、さらに記事は「教職調整額を月給の4%から引き上げることなどが検討課題だと語った」と続けている。
文科省幹部は、教員への残業代支払いの可能性を否定している。教員の残業は増える一方なのに、それに対する当然の対価である残業代の支払いを、なぜ文科省幹部は、こうもキッパリ否定するのだろうか。
教員の残業代が支払われないのは違法だとして埼玉県の公立小学校教員が県に未払い賃金として約240万円の支払いを求めた訴訟で10月1日、さいたま地裁は判決を下した。教員の請求を、司法は棄却した。
司法が棄却したのは、「給特法」という法律があるからだ。基本給の4%にあたる「教職調整額」を一律に月給に上乗せすることで、教員の残業代は支払われているとする法律が給特法、正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」である。
給特法が制定されたのは1971年で、60年代に各地で起きた超過勤務手当の支給を求める訴訟に対抗して政府・自民党がつくった法律である。そして4%という数字は、1966年に行われた全国的な教員の勤務時間調査を基に算出されている。
そのときの平均的な超過勤務、つまり残業時間は月平均「8時間」だった。その8時間相当の残業代が基本給の4%と算出されたわけだ。
平均的な残業時間が8時間だから、これを超える教員もいれば下まわる教員もいる。超える教員が多ければ、当然ながら「少なすぎる」と反対運動が起きたはずである。
しかし給特法は、多くの教員から歓迎された。月8時間の残業時間を下まわる教員が多かったためで、残業時間が少なければ少ないほど「得した」ということになったのだ。
超過勤務手当支給の訴訟も急減した。教員の不満は静まったことになる。政府・自民党にしてみれば、その目的を達することになったわけだ。
給特法では4%の教職調整額が支払われる代わりに、世間で言う残業代は支払われないことになった。管理職である校長も、一部を除いては教員に残業を命じることができないようにもなっている。
給特法によって、学校現場では残業がないことになり、残業しても月8時間以内であり、その分は教職調整額で支払われている、という仕組みができあがったわけだ。
■教員を取り巻く環境と業務内容
実際に教員の残業時間が8時間以内であれば、4%の教職調整額が支払われているのだから、法律的には問題ないことになる。ところが、この8時間が問題だ。
2016年に行われた教員実態調査では、小学校で3割、中学校では6割の教員が、過労死ラインとされる月80時間を超える残業をしている実態が明らかにされている。1966年の調査から50年が経ち、残業時間は10倍にも増えていることになる。
それにもかかわらず、教職調整額は4%のままなのだ。時間が10倍になっているのだから、教職調整額も10倍にならなければ計算が合わないのだが、そうはなっていない。
4%という一定額で、10倍もの残業時間を強いられているのが実態なのだ。まさに、「定額働かせ放題」である。
放っておけば、さらに教員の残業時間が増えていくことは明白である。新型コロナウイルス対策にしても、文科省はあれこれと指示を出してくるものの、それを実行するのに必要な人や費用の手当をするわけではない。結局、学校現場が、教員たちがやるしかない。子どもたちの健康チェックや教室の消毒などに、かなりの時間を教員は割かなくてはならなくなっている。
こんなふうに、何かやらなくてはならないとなると、教員に丸投げされるのが学校現場の実態でもある。教員の仕事は、足し算ばかりで引き算がない。その結果が、50年間で残業時間が10倍となっている現実である。
それが残業時間として認められないのは、管理職が命令した仕事ではないことになっているからだ。埼玉県の教員による訴訟でもさいたま地裁は、一部については管理職の命令があったと認定したものの、大半は管理職の命令のない仕事だったとしている。自主的にやった仕事だから、残業ではないとしたのだ。
教員の残業は、自主的なものなのだろうか。教員は、自ら望んで過労死ラインを超える残業をやっているのか。もちろん、そんなことはない。仕方なくやっている、やらされている仕事が多い。
新型コロナウイルス対策の教室の消毒にしても、本来なら教員の仕事ではない。それでもやらなければならないのは、学校の仕事を教員がやるものという慣習に教員が慣らされてきてしまったからだ。
ある教員は、「子どものために言われれば拒否できない」と言った。教員なのだから子どものためにやるのは当然だろう、と言われれば教員は拒否しない。拒否しないから、あれもこれも仕事が降ってきて、あっという間に「教員は残業するもの」という慣習ができあがり、残業時間は10倍にもなってしまった。
それなら先の『JIJI.COM』が引用した文科省幹部のコメントのように、教職調整額の引き上げが課題なのだろうか。これにも素直にうなずくことはできない。
たとえば教職調整額が10倍になったとしても、教員の不満が消えるはずもない。月に80時間も残業をして肉体的にも精神的にもボロボロになって、それが10倍の教職調整額に見合うものなのだろうか。20倍でも見合うものではない。
残業時間に見合う残業代の支払いは最低条件であり、当然のことである。それ以上に大事なことは、教員が健康を維持しながら仕事を続けられる環境を整えることである。
その大事なところを無視して、教職調整額の数字ばかりを議論してみても仕方ない。
文科省は、2022年に教員の勤務実態調査を実施し、それを基に給特法の見直しが必要かどうかも検討していくとしている。実態に合った改革を促すためにも、教員の働き方、そして給特法の実態を、いまいちど根本から検証する必要がありそうだ。