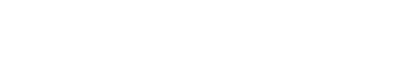全国1,101人調査で判明:渋谷はノンアル・ローアルの最先端都市MZ世代の飲み会に対するホンネとは?「あえて飲まないこともポジティブな選択」
渋谷スマートドリンキングプロジェクト発足から4年目。誰もが安心して自分らしく過ごせる空間づくりを通じて、飲みの場が多様な価値観とつながる豊かなコミュニケーションの場へと進化。

一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下渋谷未来デザイン)とスマドリ株式会社(アサヒビール株式会社と株式会社電通デジタルの合弁会社)は、渋谷区の後援のもと、2022年より展開している「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」の活動4年目となる今年、世の中の「スマートドリンキング(以下、スマドリ)」認知率が50%を超えたことを受け、MZ世代(20歳~39歳)を対象とした全国飲酒意識調査を実施しました。
今回の調査結果をもとに、1.全国・渋谷での行動・意識調査 2.飲まない人のインサイト 3.若年層が飲み会へ求めていること 4.MZ世代の特徴・インサイト の結果を特設サイトにまとめました。
特設サイト:https://shibuya-smartdrinking.jp/survey/

調査対象は「飲酒の有無」と「飲み会の好み」の掛け合わせで、以下の4タイプに分類しています。
→ 飲む・飲まないに関わらず「飲み会の場に多様な選択肢が必要」と考える声が多数
・ 渋谷エリアは全国平均に比べ、ノンアル・ローアル志向が高い(”積極的にノンアルコール飲料・低アルコール飲料を選んでいる” 平均:33.7% 渋谷:45.6% )
→ 渋谷に訪れる頻度が高い人ほど、新しい飲み方への関心が強い傾向
・お酒飲める飲めない関わらず、「飲みの場が好きな人」は多方面に気を遣っている。
・気疲れしちゃう・孤独を感じている(定性調査で見えてきた属性)
渋谷では、トレンドや情報に敏感な層が多く、SUMADORI-BAR SHIBUYAをはじめとする実体験の場も存在することで、スマートドリンキング文化が根付きやすい環境が形成されています。一方、渋谷以外のエリアでは、依然として飲用選択肢の少なさが課題として残っています。
調査実施機関:株式会社インテージ
分析協力:渋谷スマートドリンキングプロジェクト、SHIBUYA109lab.
調査方法(抽出フレーム):インターネット調査(マイティモニターよりランダムに抽出)
調査実施時期:2025年6月20日(金)~ 2025年6月23日(月)
調査地域・対象者条件:1.~3.いずれかの条件に該当
1.渋谷エリア来街者:一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に在住の20-39歳の男女かつ 月1回以上、渋谷エリアで飲食や買い物をしている
2.五大都市エリア在住者:東京23区(渋谷区除く)・札幌・名古屋・大阪・福岡市)に在住の20-39歳の男女
※「月1回以上、渋谷エリアで飲食や買い物をしている」に該当する人を除く
3.その他エリア在住者:東京23区・札幌・名古屋・大阪・福岡市を除く、全国に在住の20-39歳の男女
※「月1回以上、渋谷エリアで飲食や買い物をしている」に該当する人を除く
サンプルサイズ :n=1,101
「今回の調査では、“飲む・飲まない”どちらの立場でも、お互いを尊重しながら場を楽しもうとする姿勢が見られました。ただ、その分“探り合い”による心理的負担も感じられており、例えば、「飲みにいこう」ではなく「ご飯いこう」と誘うことで、お酒の得意不得意による場への参加ハードルをなくしていたり、お酒のペースや注文、お店選びなどはお酒が飲めない人に合わせたり、様々な工夫をしています。
「同じ時間を共有すること」において、誰かが無理をせず、でもその場の調和も乱れない場づくりをするために、企業やお店ができることはまだまだありそうです。
スマドリ株式会社
2022年6月に発足した「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」の活動も今年で3年目となり、このプロジェクトの効果と、現状のMZ世代の「飲み方」の意識、価値観を把握するべく、初の定量調査を実施しました。
「MZ世代の飲み方は、嗜好の違いを超えて『互いを尊重し合う文化』へと進化しています。
「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」では、「スマートドリンキング」の考え方が社会に広がることで、飲みの場が誰もが安心して自分らしく過ごせる空間へと進化し、多様な価値観がつながる豊かなコミュニケーションの場となることを目指して、今後も活動を展開していきます。」
一般社団法人渋谷未来デザイン 理事・事務局長 長田新子
プロジェクト発足から丸3年、着実な進展を感じています。きっかけは2021年のSOCIAL INNOVATION WEEKでのセッションでした。飲み方の多様性や現場の課題について率直な声を伺い、衝撃を受けたことを今も覚えています。『SUMADORI-BAR SHIBUYA』のオープンや大学での啓発セミナー、若い世代へのワークショップなどを通じ、「飲み方の多様性を尊重する責任あるドリンキングカルチャー」を発信してきました。
今回の調査でも、渋谷は全国と比べてノンアル・ローアル飲料の選択意向が高く、「お酒は無理して飲むものではない」という考え方が若い世代を中心に浸透していることが確認されました。これは、多様な価値を受け入れ、人とのつながりを大切にしてきた渋谷の土壌、そして産官学民での共創の成果だと感じています。
多様な仲間とともに、誰もが安心して自分らしく楽しめる新しいドリンキングカルチャーを社会に根づかせていきたいと思います。
渋谷区長 長谷部健
今回の調査で渋谷は「飲む人・飲まない人」も楽しめるような場づくり。飲料店でのレパートリーが進んでいて、飲み会を楽しんでいる人も、その場を提供する人もどちらもスマドリ思考が全国的に高いことがわかりました。渋谷が「若者が集まる街・新しいカルチャーが生まれ、派生していく街」として、今も文化を象徴する街で居続けていることを嬉しく思います。基本構想である「ちがいをちからに変える街。渋谷区」の通り、多種多様な人が楽しめる街 渋谷を目指していきます。
渋谷スマートドリンキングプロジェクト https://shibuya-smartdrinking.jp/
URL: https://fds.or.jp/
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ

一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下渋谷未来デザイン)とスマドリ株式会社(アサヒビール株式会社と株式会社電通デジタルの合弁会社)は、渋谷区の後援のもと、2022年より展開している「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」の活動4年目となる今年、世の中の「スマートドリンキング(以下、スマドリ)」認知率が50%を超えたことを受け、MZ世代(20歳~39歳)を対象とした全国飲酒意識調査を実施しました。
今回の調査結果をもとに、1.全国・渋谷での行動・意識調査 2.飲まない人のインサイト 3.若年層が飲み会へ求めていること 4.MZ世代の特徴・インサイト の結果を特設サイトにまとめました。
特設サイト:https://shibuya-smartdrinking.jp/survey/

調査対象は「飲酒の有無」と「飲み会の好み」の掛け合わせで、以下の4タイプに分類しています。
■調査サマリー
・ 全国的に「無理して飲まなくてもよい」という考えが浸透(”お酒は無理して飲むものではないと思う”の問いにはいと答えた人 全国平均69.6%)→ 飲む・飲まないに関わらず「飲み会の場に多様な選択肢が必要」と考える声が多数
・ 渋谷エリアは全国平均に比べ、ノンアル・ローアル志向が高い(”積極的にノンアルコール飲料・低アルコール飲料を選んでいる” 平均:33.7% 渋谷:45.6% )
→ 渋谷に訪れる頻度が高い人ほど、新しい飲み方への関心が強い傾向
・お酒飲める飲めない関わらず、「飲みの場が好きな人」は多方面に気を遣っている。
・気疲れしちゃう・孤独を感じている(定性調査で見えてきた属性)
渋谷では、トレンドや情報に敏感な層が多く、SUMADORI-BAR SHIBUYAをはじめとする実体験の場も存在することで、スマートドリンキング文化が根付きやすい環境が形成されています。一方、渋谷以外のエリアでは、依然として飲用選択肢の少なさが課題として残っています。
■調査概要
調査主体:スマドリ株式会社、一般社団法人渋谷未来デザイン調査実施機関:株式会社インテージ
分析協力:渋谷スマートドリンキングプロジェクト、SHIBUYA109lab.
調査方法(抽出フレーム):インターネット調査(マイティモニターよりランダムに抽出)
調査実施時期:2025年6月20日(金)~ 2025年6月23日(月)
調査地域・対象者条件:1.~3.いずれかの条件に該当
1.渋谷エリア来街者:一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に在住の20-39歳の男女かつ 月1回以上、渋谷エリアで飲食や買い物をしている
2.五大都市エリア在住者:東京23区(渋谷区除く)・札幌・名古屋・大阪・福岡市)に在住の20-39歳の男女
※「月1回以上、渋谷エリアで飲食や買い物をしている」に該当する人を除く
3.その他エリア在住者:東京23区・札幌・名古屋・大阪・福岡市を除く、全国に在住の20-39歳の男女
※「月1回以上、渋谷エリアで飲食や買い物をしている」に該当する人を除く
サンプルサイズ :n=1,101
■分析コメント
SHIBUYA109 lab. 所長 長田麻衣「今回の調査では、“飲む・飲まない”どちらの立場でも、お互いを尊重しながら場を楽しもうとする姿勢が見られました。ただ、その分“探り合い”による心理的負担も感じられており、例えば、「飲みにいこう」ではなく「ご飯いこう」と誘うことで、お酒の得意不得意による場への参加ハードルをなくしていたり、お酒のペースや注文、お店選びなどはお酒が飲めない人に合わせたり、様々な工夫をしています。
「同じ時間を共有すること」において、誰かが無理をせず、でもその場の調和も乱れない場づくりをするために、企業やお店ができることはまだまだありそうです。
スマドリ株式会社
2022年6月に発足した「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」の活動も今年で3年目となり、このプロジェクトの効果と、現状のMZ世代の「飲み方」の意識、価値観を把握するべく、初の定量調査を実施しました。
「MZ世代の飲み方は、嗜好の違いを超えて『互いを尊重し合う文化』へと進化しています。
「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」では、「スマートドリンキング」の考え方が社会に広がることで、飲みの場が誰もが安心して自分らしく過ごせる空間へと進化し、多様な価値観がつながる豊かなコミュニケーションの場となることを目指して、今後も活動を展開していきます。」
一般社団法人渋谷未来デザイン 理事・事務局長 長田新子
プロジェクト発足から丸3年、着実な進展を感じています。きっかけは2021年のSOCIAL INNOVATION WEEKでのセッションでした。飲み方の多様性や現場の課題について率直な声を伺い、衝撃を受けたことを今も覚えています。『SUMADORI-BAR SHIBUYA』のオープンや大学での啓発セミナー、若い世代へのワークショップなどを通じ、「飲み方の多様性を尊重する責任あるドリンキングカルチャー」を発信してきました。
今回の調査でも、渋谷は全国と比べてノンアル・ローアル飲料の選択意向が高く、「お酒は無理して飲むものではない」という考え方が若い世代を中心に浸透していることが確認されました。これは、多様な価値を受け入れ、人とのつながりを大切にしてきた渋谷の土壌、そして産官学民での共創の成果だと感じています。
多様な仲間とともに、誰もが安心して自分らしく楽しめる新しいドリンキングカルチャーを社会に根づかせていきたいと思います。
渋谷区長 長谷部健
今回の調査で渋谷は「飲む人・飲まない人」も楽しめるような場づくり。飲料店でのレパートリーが進んでいて、飲み会を楽しんでいる人も、その場を提供する人もどちらもスマドリ思考が全国的に高いことがわかりました。渋谷が「若者が集まる街・新しいカルチャーが生まれ、派生していく街」として、今も文化を象徴する街で居続けていることを嬉しく思います。基本構想である「ちがいをちからに変える街。渋谷区」の通り、多種多様な人が楽しめる街 渋谷を目指していきます。
<渋谷スマートドリンキングプロジェクトについて>
アサヒビール株式会社と株式会社電通デジタルの合弁会社であるスマドリ株式会社と、渋谷区の外郭団体である一般社団法人渋谷未来デザインが中核となって推進し、渋谷を拠点とする企業や自治体が繋がり、生まれたプロジェクト。企業や大学・団体と連携し、適正飲酒啓発セミナー・各種ワークショップ・情報発信イベントを実施することで、社会課題解決や飲み方の多様性を尊重し合える社会の実現に取り組んでいます。渋谷スマートドリンキングプロジェクト https://shibuya-smartdrinking.jp/
<一般社団法人渋谷未来デザインについて>
渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。URL: https://fds.or.jp/
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ