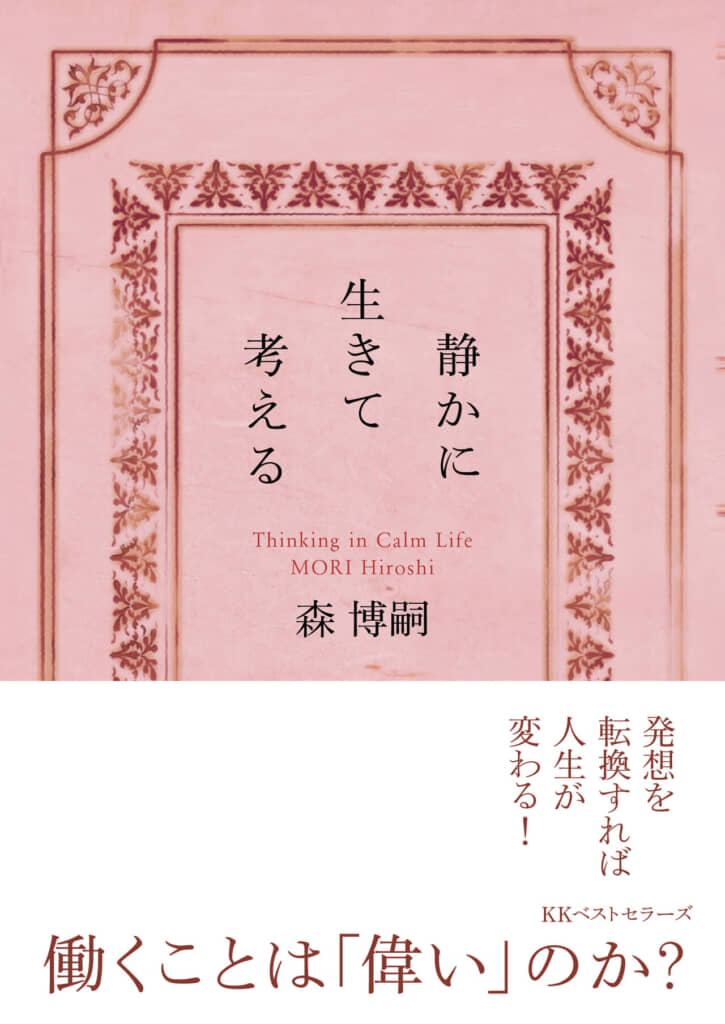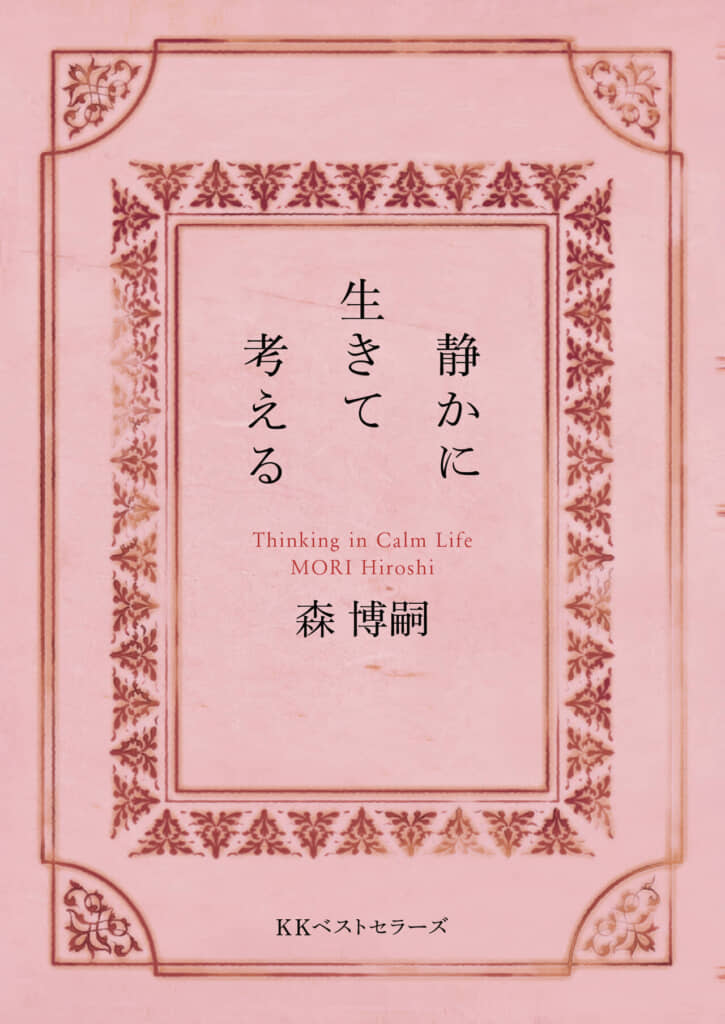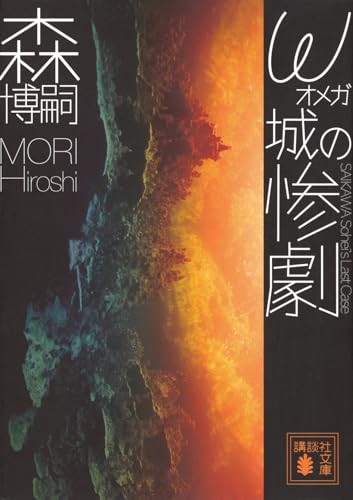語学や数学を学ぶ理由【森博嗣】新連載「道草の道標」第9回
森博嗣 新連載エッセィ「道草の道標」第9回
【言語に支配される文化と思想】
思想というものは言語に支配されている。哲学を学んだことはないけれど、遠望しただけで、そう感じる。
言語を学ぶ理由というのは、かつては主として外国の文化とのコミュニケーションだった。今はその理由はほぼ消失した。スマホを持っていれば、外国人と会話でき、文章を読むことができるからだ。けれど、だからといって外国語を学ぶ意味がなくなったと思うのは早計というもの。自国語を学ぶのだって、会話や本を読むだけが目的ではないのと同様で、つまりは、その言語の生い立ちというか、その国の文化を理解することにつながっている。思想や思考方法の主要なツールである言語から、その言葉を使って考える人たちの論理の組立てが想像できるし、着目点や意識する範囲が異なることも学べる。
英語などには、名詞を説明するために冠詞や複数形、関係代名詞がある。これらが、精密な状況伝達を可能にしている。一方、日本語には豊富なオノマトペがあって、雰囲気や気持ちを伝えやすい。
僕は、学校や大学で英語とドイツ語を学んだ。ドイツ語はさっぱり忘れてしまったけれど、それを学習したことで、英語というものの特殊さ(たとえば、発音がスペルどおりではない点など)を知ったし、発音がけっこう難しい部類なのも理解できた。中国語は習ったことがないけれど、中学と高校で漢文の授業があったから、文法は理解できたし、また、発音によってリズムを取る美しさも知った。どうして、ゲーテがもてはやされるのかわかったし、また、漢詩から影響を受けた日本語の名文も親しめるようになった。言語を学ぶことは、そういった文化と思想に接近する道なのである。
ちなみに、語学だけではない。数学や物理学や化学を学ぶことも、文化と思想の基盤となる。論理的な思考や想像は、数学を構造として、物理学や化学を材料にして組み立てられるから、その人物の思想を形作るし、ものごとの道理を見極める基礎能力を育む。これら理系の学習を切り離した教育は、文化の半分を教えていないといえる。
とはいえ、逆に、そういった言語や数理によって、文化や思想が支配されている点にときどき意識を向けることも大事だ。何故なら、その支配を断ち切るような発想が必要な場合もあるからである。発想は思考のジャンプであり、ジャンプするためには、ジャンプ先が必要で、多くの着地点を持っている人ほど、発想のチャンスが増える。
その発想の着地点は、ギャップがあるのに、なんらかのリンクで導かれる。そのリンクを作るものは、つまりは「道理」なのである。たとえば、道理がなく単なる言葉の発音の類似だけで発想すると駄洒落になる。これも一つの発想でありジャンプだけれど、道理の洒落は、あるときは閉塞感を吹き飛ばすような起爆的な役割を果たす。
KEYWORDS:
✴︎新連載「道草の道標」のご質問箱✴︎
《森博嗣先生へのご質問はこちらからお寄せください!》
https://www.kk-bestsellers.com/contact
上記 「BEST T!MES」 問い合わせフォームのリンクから、
森博嗣先生へのご質問を承ります。
★テーマも質問もできるだけ簡潔に(100文字程度)でお願いいたします(文章も多少修正して紹介されます)。
★「BEST T!MES」お問い合わせフォームの「問い合わせ項目」に【道草】と記入しお送り下さい。
★質問者のお名前や個人情報が記事に出ることは一切ありません。ご安心ください。
✴︎KKベストセラーズ 森博嗣の最新刊✴︎
『静かに生きて考える 』文庫版
✴︎KKベストセラーズ 森博嗣の好評既刊✴︎
『日常のフローチャート
※上のカバー画像をクリックするとAmazonページにジャンプします