渋谷陽一とオジー・オズボーンの死が示す虚実の境界線【近田春夫×適菜収】
【近田春夫×適菜収】新連載「言葉とハサミは使いよう」第8回
現実が虚構を超えた。そんな言葉が相応しい参院選の選挙結果になった。とはいえ世の中に存在する虚実皮膜を楽しめる精神がなくては現代はより生きにくくなるだろう。20世紀末の時点で、音楽はいずれタダになると予言していた音楽家近田春夫氏と、近代大衆社会の末期症状を描き出した『日本崩壊 百の兆候』(KKベストセラーズ)が絶賛発売中の作家適菜氏による異色LINE対談。連載「言葉とハサミは使いよう」第8回。

■渋谷陽一の死と「ファン」の心理
適菜:渋谷陽一、死んじゃいましたね。近田さんは接点はあったのですか?
近田:うん。あいつとは学年は僕の方がひとつ上なんだけど、同い年なのよ。そもそも渋谷の大学の同級生が、内田裕也さんのマネージャーだった大久保という男で、こいつはその後、土井たか子の秘書になって、東京都議会議員になったんだけどさぁ、そんな縁で20代の前半から付き合いがあったのよ。
適菜:大久保青志さんですね。1972年に『ロッキング・オン』創刊にも携わった。
近田:大久保との付き合いは随分になるよ。
適菜:今、思い出すと、渋谷陽一という名前を知ったのは中学生の頃だったと思います。いろいろな人と対談していますよね。村上龍と対談しているのを読んだ記憶もあります。高校1年のときにプリンスの『Sign o’ the Times』を買って、その解説が渋谷だったと記憶しています。記憶違いかもしれませんが。『Sign o’ the Times』の歴史的位置づけについて、かなり正確なことを書いていたような気がします。その後、吉本隆明に近づいて行って、あれはどうかなと思ったこともありました。
近田:俺は渋谷とは全く評論というものに対する考えが違っていて、要するに俺は作品至上主義なんだけど、あいつはアーティストがどういう人間なのかということなのよ。それって芸能人の日常にスポットライト当てる女性週刊誌的好奇心でしょ? アプローチが下世話だよ。そのスタンスだと、全く音楽聞かなくても原稿書けるじゃん。その方がファンは喜ぶし。
適菜:だから、吉本のファンになってしまう。編集者としての視点ではなくて、ファンの視点で吉本の本を作ってしまう。
近田:批評にファンの視点って根本的に意味なさないじゃんさ。情緒は最後の味付け程度だと思うのよ。なぜそう感じるのか? それはこういった構造のゆえである、というのが評論だって俺は思ってるのよ。昔、徳大寺有恒って言う自動車評論家がいてさあ、結構雑誌でよく読んでいた。そしたらある時、「イタリア車はよく壊れる、そこがいい。国産車と違って壊れ方に色気がある」みたいなことを言っていて。それを言ったら評論て意味なさないじゃん。
適菜:イタリア車、他に褒めるところ、なかったのでしょうか? まあ、音楽評論でも、「首を痛めた」とか「ヘルニアになった」とか、そういうことにスポットをあてる評論(もどき)みたいなのがありますね。
近田:国産車に同じような欠陥があれば手厳しいんだから。つまり、評論の前にイタリア車に対する偏愛の方が優ってるという。それでまた、同調する編集者とかも結構いて。
適菜:ファンになってしまうと、周囲のことに目がいかなくなる。アイドルが自殺すると、ファンが後追い自殺するのもそうですね。どこかおかしくならないとファンにはならないのかもしれない。最近はあまり見かけませんが、80年代くらいは「聖子命」みたいなのがありました。
近田:自分の夢中になっている対象の結婚を絶対に許さないってのは、未だにあるからねぇ。しかし、アイドルは恋愛禁止って、人権的に問題ないのかなぁ? だってセックスしたらクビってことでしょ?
適菜:近田さんはアイドルとは仕事はいろいろあったのですか?
近田:ないですね。唯一「ラストアイドル」っていう番組の中でGood Tearsというグループに「へえ、そーお?」というのを詞曲書いたのだけかなぁ? あと田原俊彦のデビューアルバムに書いたのぐらい?
適菜:なんて曲ですか?
近田:「イン・ザ・プラネット」と「10代の傷跡」です。それと西城秀樹「スウィートソウルアクション」「アメイジング・ガール」も書いたか。
適菜:すごいキャリアですね。
近田:そりゃ74歳だからね。
適菜:田原俊彦は1980年にピンで歌手デビューみたいですね。
近田:最初はドラマ「3年B組金八先生」で役者デビューだったかなぁ?
適菜:いろいろ記憶が蘇ってきました。大学生のころ、金八マニアの先輩がいて、一時期、よく私の部屋に金八のビデオを持ってきて、一緒に見ていました。私は見たくなかったのですが、ほとんど強制的に見せられました。あれは苦痛でした。
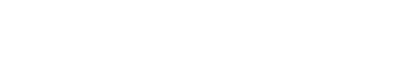
-1-697x1024.jpg)
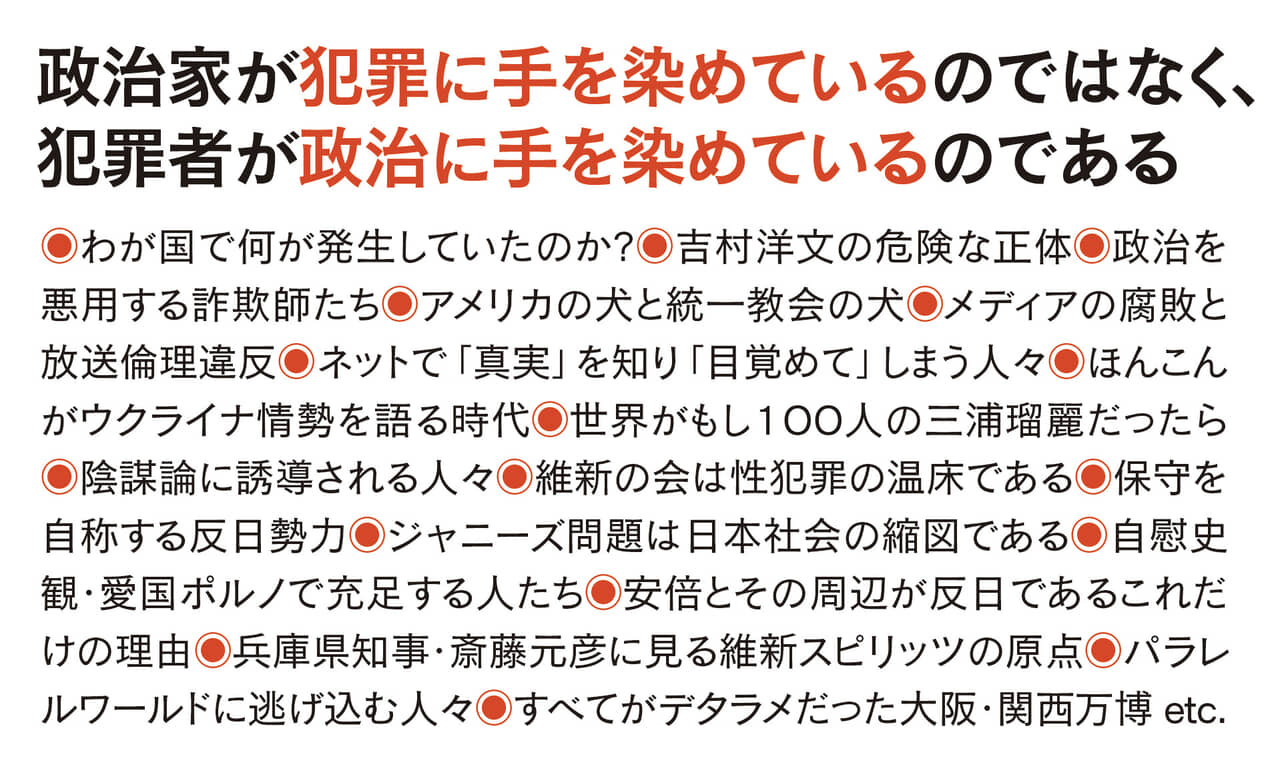
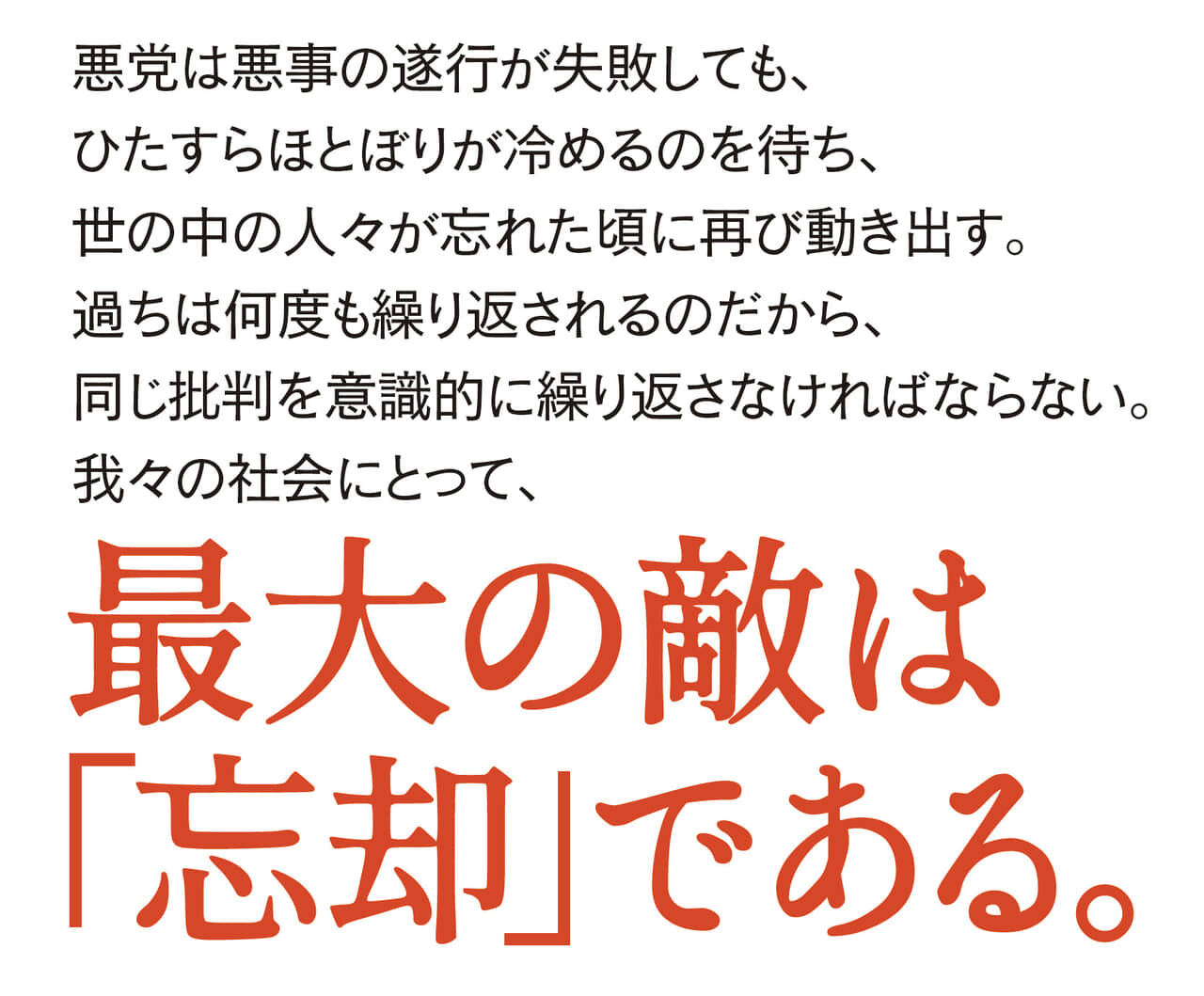
-697x1024.jpg)








