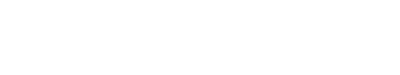「ハラスメント」「キャンセル・カルチャー」「マインド・コントロール」 言葉の定義を知らず、濫用して騒ぐバカなネット民に告ぐ!【仲正昌樹】
◾️有名人をターゲットにしたキャンセル運動の内実
また、実際に「ハラスメント」であったかどうか認定するには、最低限、①それが組織の運営に必要な指示・指導の範囲を逸脱していたかどうか、②相手が本当はそれを嫌がっていた、受け入れていなかったことを認識できる指標はあったのか――の二点ははっきりさせる必要がある。「本人が嫌だと思えば、ハラスメントだ」という言い方があるが、それはあまりにミスリーディングだ。正確には、「本人が嫌だと思ったのであれば、どういう行為であれ、ハラスメントに当たる可能性が生じる」であって、ハラスメントを受けたと言う側の言い分がそのまま通るはずがない。①と②について第三者的な視点から検討しなければならない。法学では、「通常(理性)人 reasonable man」の基準と言う。
ただ、「第三者」と言っても、本当に客観的な立場の第三者などいない。よく言われるように、たとえ悪意やエコひいきのつもりはなくても、男性は男性の、女性は女性の、会社経営者は経営者の、労働者は労働者の、医者は医者の、患者は患者の、〇〇人は他民族ではなく同じ〇〇人の視点に同化して判断しがちだ。そのため、どういうケースでどういう人が判定すべきか、なかなか正解は見つからない。被害者として名乗り出た人が、本当にその時点で、権力ゆえの圧力で抵抗しなかったのか誰もが納得するような仕方で認定するのは至難の技である。
本来は認定が難しいはずなのに、有名人をターゲットにしたキャンセル運動では、ハラスメントを受けたという“被害者”が名乗り出ると、「被害者が名乗り出ているのだから、何もなかったはずはない」という雑な断定によって、“より有名人”である方がハラスメントをしていたと決めつけられ、裁判も正規の調査もないうちに激しい攻撃に晒される。これは、「ハラスメント」概念の水増しである。本来の適正な意味で使うようにしないと、一方的なネットリンチの口実にされるし、インフレ・濫用のために「ハラスメント」という言葉が軽くなっている。