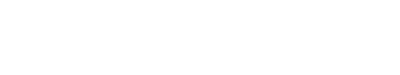「ハラスメント」「キャンセル・カルチャー」「マインド・コントロール」 言葉の定義を知らず、濫用して騒ぐバカなネット民に告ぐ!【仲正昌樹】
◾️「パワハラ」に明確な基準はあるのか?
厚生労働省のHPでは、「パワー・ハラスメント」は、「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの」と定義されている。「セクハラ」は、その一部と見なされているようで、「「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること」とされている。
こうした定義からも、組織的な権力関係があり、上下関係ゆえに一方の要求、願望を他方が拒否できない状況での嫌がらせや押し付けを拒みにくい状況を念頭に置いているのは明らかだろう。ただ、「ハラスメント」は、通常の法律・道徳概念のように、これをやったらアウトで、これならセーフという明確な基準がない。どうして、そういう曖昧なものが法律用語に参入してきたかというと、それは、近代社会では当人同士の「合意」が、合法性・正当性の基準になっているからだ。
他人の身体にメスを入れたり、医薬品の実験材料にするのは、原則違法だが、本人が合意していれば合法である。格闘して相手にケガをさせれば、犯罪であれば、事前に試合に関する合意が成立していれば、合法である。暴力でセックスを強いれば強姦罪になるが、相手が暴力的に振る舞うことについて合意していれば、原則罪に問われない。
ただ、形の上では「合意」した、あるいは、明確な拒絶の意志を示していなくても、相手の権力を恐れてのことで、実質的な合意はなく、強制によるものではないか、と疑われる場合もあることを私たちは経験的に知っている。そこで、形式的な「合意」があっても、権力関係による圧力が明白な場合は、実際には強制であり、刑法上の犯罪であるかは別にして、違法だと認定するために、「ハラスメント」という概念が導入されたのである。
「ハラスメント」を適用する際の基本はあくまで、組織的な権力関係があることと、それゆえに合意があったかどうかが疑わしい状況があったということだ。何か個人的なトラブルがあり、一方が社会的地位や知名度が高かったら、それだけでハラスメントになることはあり得ない。そんなことを言い出したら、全ての争いごとはハラスメントになってしまう。