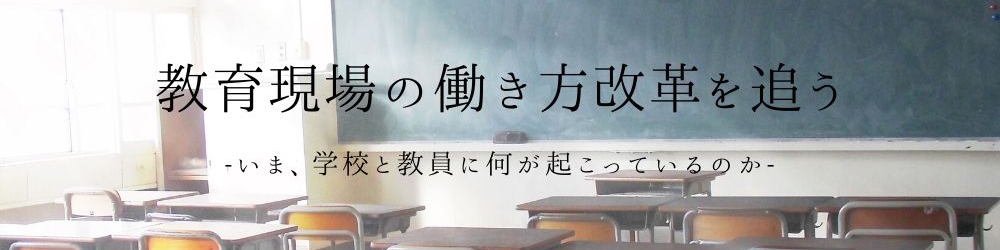このままの「給特法」改正案で何が「前進」するのか
【第5回】学校と教員に何が起こっているのか -教育現場の働き方改革を追う-
◆鵜呑みにできない附帯決議
「教職員給与特別措置法(給特法)」改正案は11月22日に参議院で審議入りとなり、与党は12月9日の会期末までの成立を目指している。改正案の柱は、教員の勤務時間を年単位で管理する「変形労働時間制」の導入である。
しかし、変形労働時間制の実施については疑問が持たれており、参議院での審議においてもその議論が中心になっている。衆議院でも同様だ。実施についての疑問が呈されたにもかかわらず、結局は大きな混乱もなく通過してしまった。おそらくは、参議院でも混乱なく通過し、成立ということになるのだろう。
なぜ、反対の声が大きくならないのだろうか。
その疑問をある教職員団体の幹部にぶつけると、「今回の改正案は、完全とは言えなくても、一歩前進にはつながると捉えています」との答えが返ってきた。さらに彼は、「今回は附帯決議もありますから、具体的に実施されていくと思います」とも語った。
衆議院を通過した給特法改正案には、たしかに「附帯決議」が付けられている。国会の委員会で法案を可決する際に、委員会の意志を表明するものと位置づけられている。つまり給特法の附帯決議は、衆議院文部科学委員会が法案を可決するにあたって、委員会での議論を反映させたものである。
附帯決議の冒頭には「政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特設の配慮すべきである」と記され、9項目が掲げられている。その4項目目には、「1年単位の変形労働時間制の導入の前提として、現状の教員職員の長時間勤務の実体改善を図る」としている。長時間勤務になってしまっている現状を改善するために変形労働時間制を導入する、と念押ししていることになる。
変形労働時間制の導入が現実的かどうかの疑問はあったにしても、何らかの「前進」を先の教職員団体の幹部は感じているようだ。国会で教員の働き方改革が取り上げられていること自体に「前進」を感じている教員は、実は多いような気がする。
しかし、本当に光明となるのか、もう少し冷静になって判断していかなければならないような気もする。たとえば附帯決議については、「1年単位の変形労働時間制は、全ての教員職員に対して画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること」という文言がある。
つまり、附帯決議のこの文章にそって実際に条例等ができた場合、「育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者」は利用できるが、多くの教員は利用できない制度となってしまうかもしれないのだ。
◆教員の残業時間は減らせない
そもそも、変形労働時間制を誰もが利用するようになれば、学校では夏休みなどに多くの教員が休んでいる状態となる。現在の学校現場では、夏休みであっても教員の仕事はたくさんある。現状のままで、誰もが変形労働時間制を利用できるようになれば、学校がまわらなくなるのは確実である。
だから、変形労働時間制の適用を限定するようなことが、わざわざ附帯決議に盛り込まれているとも考えられる。それを、「前進」と呼んでもいいのだろうか。「まとまった休みがとれるのだから、普段の日の残業(超過勤務)は仕方ない」という流れになってしまいかねない。
「そうは言っても、残業時間はきっちり定められて規制されることになるわけですから」と、先の教職員団体の幹部は言う。今年1月に文科省は、教員の残業時間の上限目標を月45時間とするガイドラインを策定している。これを給特法改正案では、ガイドラインから「指針」に格上げして、法的拘束力を持たせることも法案に盛り込んでいる。
さらに衆議院の附帯決議では、「1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、連続労働日数原則6日以内、労働時間の上限1日10時間・1週間52時間、労働日数の上限年間280日等とされている労働基準法施行規則の水準に沿って文部科学省令を定めること」となっている。文科省のガイドラインより、さらに残業時間を減らすことを求めているわけだ。
どちらにしても、これも現実的ではない。
月80時間の過労死ラインを超える残業時間をこなしている教員が小学校で3割以上、中学校では6割を超えているのが現状である。月100時間を超える残業時間も、珍しいことではない。
また、給特法が改正されて残業時間に上限が設けられ、その上限が守られることになれば、それこそ学校現場が機能不全に陥ってしまうことは目に見えている。
機能不全になることを、学校の管理者や教育委員会、そして文科省は望まない。給特法での上限を守る建前をとりながら、裏で教員に仕事を強制することになるだろう。
給特法の見直しが、教員の働き方改革において「前進」となるのかどうかはうたがわしい。