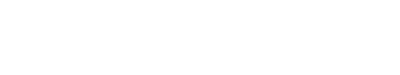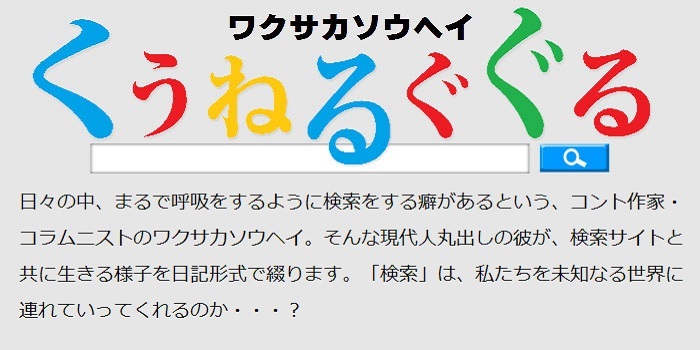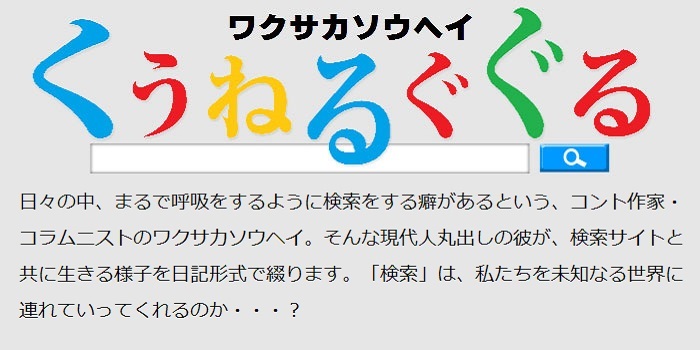第43回:「コメンテーター」
<第43回>
7月×日
【「コメンテーター」】
ニコニコ生放送の、とある番組から出演依頼が届いた。
某映画の宣伝番組で、貴殿にはコメンテーターとしてご出演いただきたい。メールの文面には、そう書かれていた。
すぐさま「コメンテーター」でグーグル検索。
ニコニコ大百科によると「コメンテーターとは自分の知識を基に、見解や意見を発言する人」とあった。
知識!見解!意見!発言!
なんと六大学卒な仕事なのだろう、コメンテーター!知的な香りしかしないではないか、コメンテーター!
そうか、自分はコメンテーターだったのか。すぐさま僕は舞い上がった。爪にいつもちょっとした粘土が入り込んでいるだけの人間だと思っていたが、なんだ、自分はコメンテーターだったのだ。
教室の天井にいつもヤモリがはりついている、授業中に隣のマンションに住んでいる若夫婦のあえぎ声が聞こえてくる、用務員さんを雇う金がないので生徒に掃除をさせる、といった「刑務所か」みたいな夜間学校が最終学歴である自分。なのに僕は「卒業式の日は黒くて四角い帽子を空に向かって投げました。そうです、わたしがコメンテーターです」みたいなツラを浮かべて、ニコ生のスタジオへと向かった。「コメンテーター」という甘い響きが作り出した虚構の偏差値が、僕に根拠のない自信を与えていた。
生放送の収録が始まった。
僕の隣には、同じくコメンテーターとして、初老の大学教授の方が座っていた。
隣に大学教授。この状況にまた自分は気をよくした。遠足のバスでは必ず隣の子がゲロを吐いたり、総武線で寝ていたらいつのまにか隣にホームレスが座っていたりと、隣に関してはひどく輝きのない人生を送ってきたが、そうか、ついに隣に大学教授か。「となりのダイガクキョウジュ」。もしここがスタジオではなくバス停であったのなら、きっとその初対面の大学教授に傘を貸していたことだろう。ああ、それは森へのパスポート…。
うっとりと夢想を広げているうちに、いつの間にか大学教授が喋っていた。理路整然とした口ぶりで、映画の魅力を的確に伝えている。なるほど、ははん、大学教授はこの映画をそういう視点で観たわけね、やるじゃない、じゃあ僕は違う切り口でいこうかな、ところでキミはどこの研究室出身?などとたいした気になってそれを受け、いよいよ自分が喋る番となった。
「この映画の一番の見所を教えてください」女性MCの人が、僕に話を振ってくる。
「そうですね…」僕は落ち着いた口ぶりで一呼吸置いたのち、語り始めた。視聴者よ、時は来た!わたしの頭脳からこんこんと湧き出る知識の泉に、手を伸ばすがよい!
「Hなシーンが、良かったですね」
…あれ?おかしいな?いま、麩菓子みたいにすごくスカスカなことを言ってなかったか?
これ、知的なコメントか?
「Hなシーンのどこが良かったんですか?」MCの人が尋ねてきた。
「いや、まあ、唐突にHなシーンが登場していて、まあHなシーンはあるだろうな、とは思ってたんですけど、ほんと、唐突で。あの、これってもっと喋らなきゃダメですか?」
こうして僕の主たる出番は終わった。
その後も生放送は続き、時折MCの人が話を振ってきたのだが、そのたびに僕は5ペソのようなコメントを返した。
MC「この映画は過激な内容を含みますが、果たしてDVD化されるでしょうか?」
僕「(すごく熟考する間があってから)…うーん、考えたこともないです」
MC「ではここで映画に関するプレゼン対決コーナーです。勝った方には、特製のトートバッグをプレゼントします」
僕「(本気で)え?あそこにあるトートバッグ、貰えるんですか?ほんとに?無料で?欲しい!欲しい!え、ほんとに無料で?」
MC「今日のニコ生、楽しまれてますか?」
僕「ええ。生きてきた中で、一番楽しい時間です」
おかしい。思っていたのと、違う。
もっと自動的に知的なコメントが溢れてくるものだとばかり思っていたのに、実際に口から出てくるのは、たまごボーロの食べこぼしみたいなコメントばかり。
ああ、忘れてた。自分は、バカだったんだ。
自分がバカだということを、バカだから、忘れていた。
途端に嫌な汗が出た。
このニコ生は、2000人以上が視聴している。
そんなに大勢の人にバカがバレるだなんて。絶対に避けたい。
なんとかしなければ。
番組は、MCと大学教授のトークが繰り広げられていた。
よし、ここに割って入り、知的なコメントを言うことで、いままでの空っぽな発言を帳消しにするのだ!
「あの、さっきから親密そうに喋っていますが、おふたりは付き合っているんですか?」
こうして番組は、エンディングを迎えた。
スタジオを出ようとしたら、大雨が降っていた。
「お疲れ様」
大学教授が傘を広げながら、雨宿りしている僕の横を通り過ぎていった。
傘を貸してほしかったが、なにも言えなかった。
*本連載は、毎週水曜日に更新予定です。
*本連載に関するご意見・ご要望は「kkbest.books■gmail.com」までお送りください(■を@に変えてください)