若者と年寄りはどこがどう違う?【森博嗣】新連載「道草の道標」第6回
森博嗣 新連載エッセィ「道草の道標」第6回
森博嗣先生が日々巡らせておられる思索の数々。できるだけ取りこぼさず、言葉の結晶として残したい。森先生のエッセィを読み続けたい。なぜなら、自分の内から湧き上がる力を感じられるから。どれだけ道に迷い込み、彷徨ったとしても、諦めず前に進んでいけることができるから。珠玉の連載エッセィ第4弾「道草の道標」。第6回は「若者と年寄りはどこがどう違う?」
第6回 若者と年寄りはどこがどう違う?
【飽き性なのか没頭するタイプなのか】
自分のことをときどき分析して、いったいどういう人間なのだろうか、と考えるようにしている。そして、周囲の人々との差異を評価し、修正すべきか、あるいは放置すべきか、などとも考察。若いときほど修正が多く、最近ではほぼ放置しているような気がする。他者を気にするようなことはないけれど、見せかけ上は周囲に合わせた方が有利なことが社会では多い。わざわざ不利なままにするほど愚かではないから、簡単に直せるところは、人前に出るときだけ演じるようにした。これによって、ちゃんと就職できたし、ちゃんと仕事を続けることもできた。案外上手くいったと思う。
基本的に飽き性なのは確かで、あらゆるものが長続きしない。どんどん興味の対象が移ってしまうから、同じものにずっと集中していられない。子供の頃に顕著だった。大人から何度も指摘され、このままではちょっとまずいかなと理解したものの、なかなか一つのことに長く関われない癖を直すことはできなかった。
ただ、毎日同じノルマを繰り返すことに抵抗は少なく、日々のスケジュールを決めたら、平日も週末もずっとそれを厳守し持続できた。つまり、同じことを長時間はできないが、少しずつ分割すればなんとかなる、ということのようだった。この傾向を自分で発見し、以後なるべく短時間でつぎつぎ異なる課題に取り組む手法が効果的だと考えた。
また、非常に興味のある対象であれば集中していられるし、ほかの行為を排除して何十時間でも一つの課題に取り組めることもわかった。大学に入ってから、それができることを発見した。この場合の行為とは、主に思考すること、躰ではなく頭を使うことに限られる。発見できたのは、コンピュータのプログラミングを始めたからで、この場合指は少し動くけれど、主に目と頭を使う。指と目は疲れるが、頭は数十時間でも疲れるようなことはなかった。睡眠も食事もしないで2日間以上続けることもあった。なにかを飲んだり、トイレにいくのさえ面倒になるほど、どっぷりゾーンに入ることができた。
集中力があるのか、それとも飽き性なのか、どちらなのかわからない。興味のあること、解決しなければならない不思議さが目の前にあれば集中できるが、たとえば文章を書くなどの作業や労働になると、長くは続かない。工作は面白ければ半日くらいは没頭できる。人と議論をしたり話をしたりするのは2時間くらいが限界か。すぐに別のことをしたくなってしまう。こういった個人の仕様というのは、簡単に修正できないものだ。
KEYWORDS:
✴︎新連載「道草の道標」のご質問箱✴︎
《森博嗣先生へのご質問はこちらからお寄せください!》
https://www.kk-bestsellers.com/contact
上記 「BEST T!MES」 問い合わせフォームのリンクから、
森博嗣先生へのご質問を承ります。
★テーマも質問もできるだけ簡潔に(100文字程度)でお願いいたします(文章も多少修正して紹介されます)。
★「BEST T!MES」お問い合わせフォームの「問い合わせ項目」に【道草】と記入しお送り下さい。
★質問者のお名前や個人情報が記事に出ることは一切ありません。ご安心ください。
✴︎KKベストセラーズ 森博嗣の最新刊✴︎
『静かに生きて考える 』文庫版
✴︎KKベストセラーズ 森博嗣の好評既刊✴︎
『日常のフローチャート
※上のカバー画像をクリックするとAmazonページにジャンプします
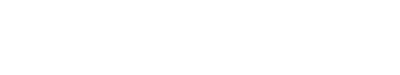

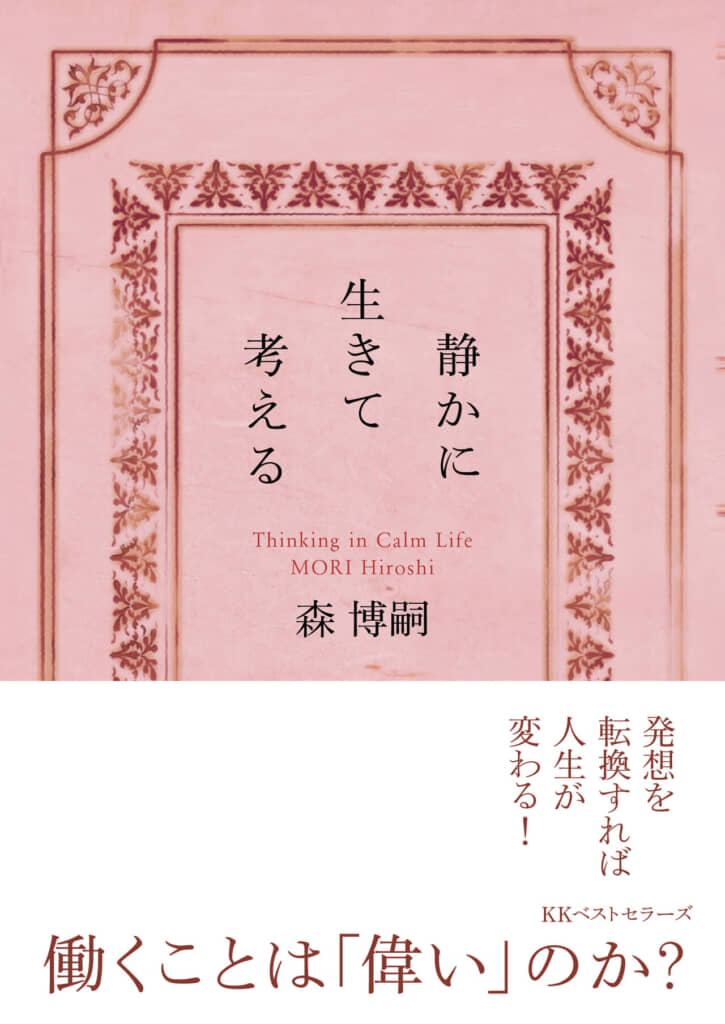
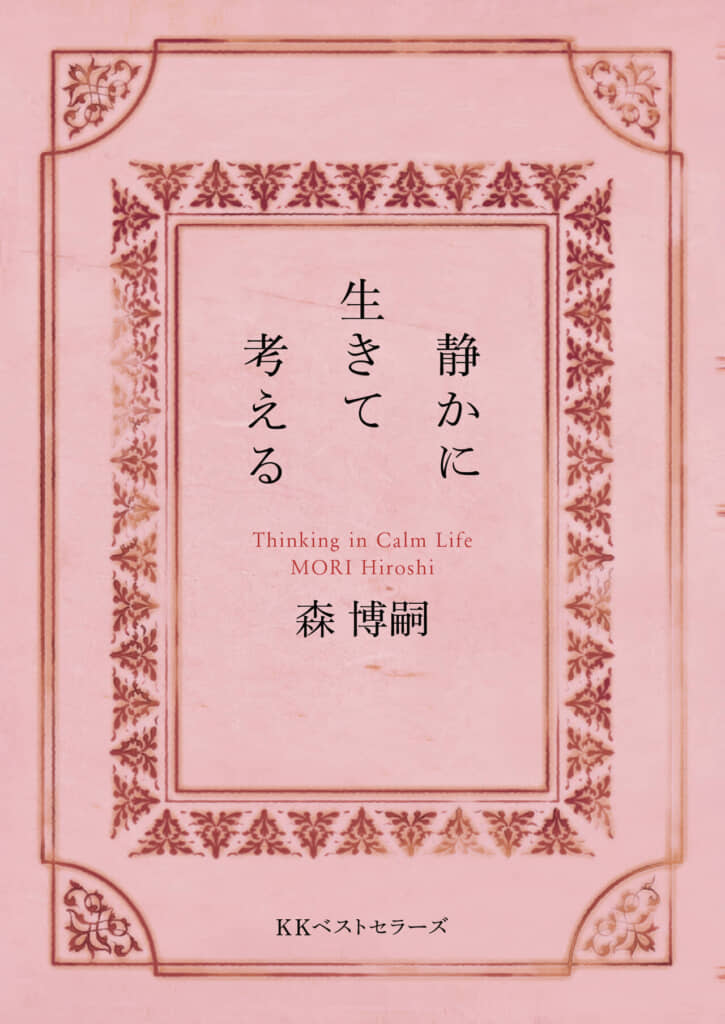





![充実した人生に唯一必要なもの【森博嗣】連載「日常のフローチャート」第35回[最終回]](https://www.kk-bestsellers.com/wp-content/uploads/写真35-1.jpg)



