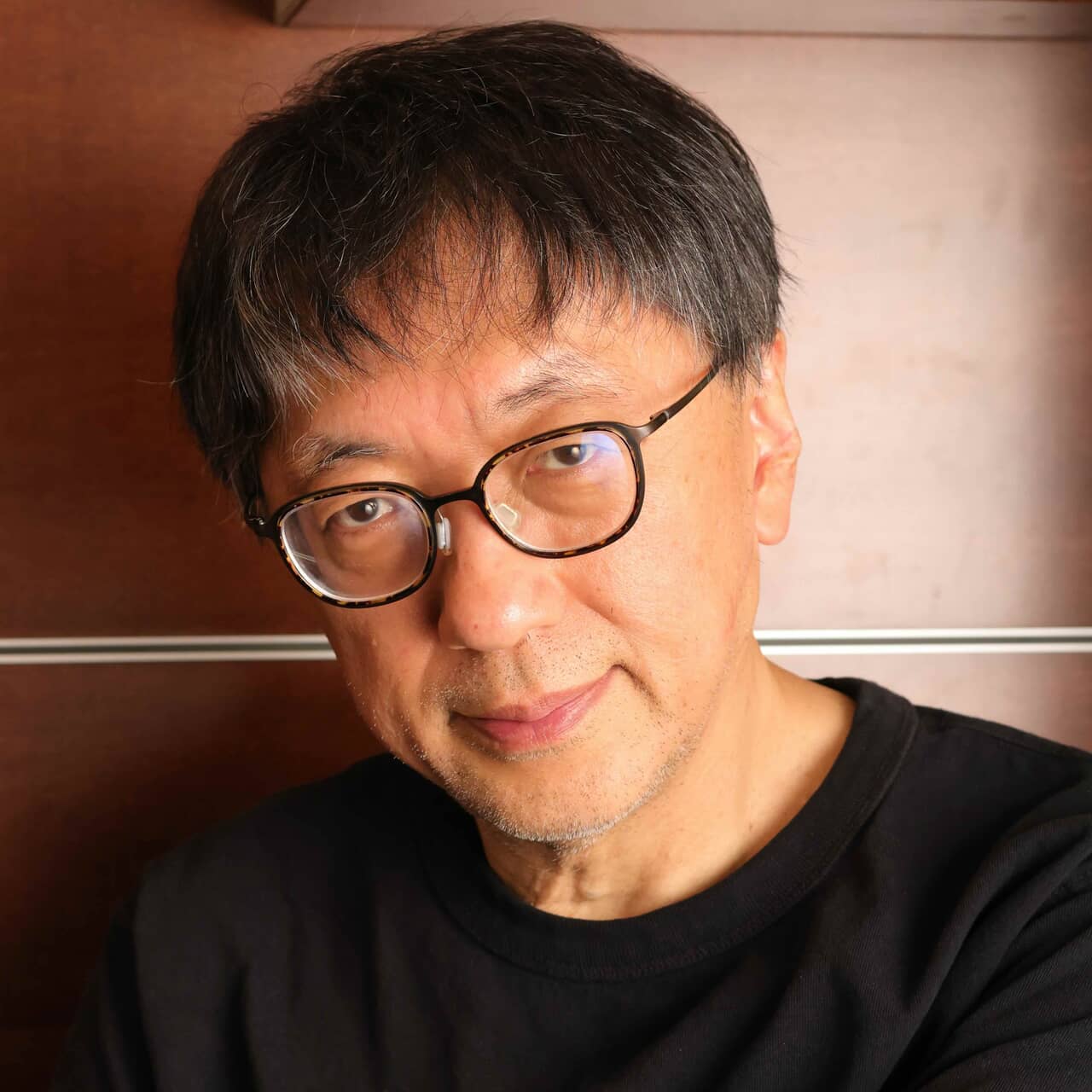小泉進次郎の登場は「人事」ではなく「次期総裁選」だ 【林直人】

突如辞任を表明した農林水産大臣。その後任に小泉進次郎氏が就任した。このニュースは一見すると単なる人事交代のように見えるが、実態ははるかに深く、構造的な転換の端緒である。
従来の農林水産行政は、農協との協調や既得権の保護に軸足を置いた保守的な運営が続いてきた。前任大臣もまた、大胆な農政改革には慎重な姿勢を崩さず、変化を避ける政治姿勢が際立っていた。
しかし、小泉進次郎の登場はまったく異なるメッセージを発している。彼は、自民党農林部会の中心人物として長年にわたり「開かれた農業」「競争力ある農政」を提唱し続けてきた、いわば農政改革のシンボルだ。
このタイミングでの任命の背景には、日米の貿易交渉がある。特にトランプ政権時代、アメリカは日本に対し、農産物市場の一層の開放を強く求めてきた。関税引き下げや輸入枠拡大など、厳しい要求が続き、日本側も対応に苦慮してきた。
日本の農業市場の背後には、JAグループが展開する巨大な金融・物流ネットワークがある。その経済規模は国内最大級であり、単なる農業政策の枠を超えて、金融市場や国際経済政策とも密接に結びついている。
この文脈の中で、小泉氏のような「構造改革を担える人物」が農林水産大臣に就任したことは、日本政府としての意思表示に他ならない。
特筆すべきは、この動きが小石河連合と呼ばれた政治潮流と重なる点だ。小泉進次郎、河野太郎といった改革志向の政治家たちがかつて構想していた「ポスト自民党的」な政治モデルが、今まさに現実の政権運営に投影され始めている。
この変化は、岸田政権の延長線上ではなく、新たな政治段階への突入を意味する。平成的な「調整型・護送船団モデル」から脱却し、競争・開放・民間活力を柱とする令和型の国家運営へ——。
国債利回りが上昇し、財政構造に対する国際的な警戒感が強まる中、日本経済はこれまでの惰性では生き残れない。1997年の韓国のIMF危機がもたらした「強制改革」のように、いまや日本も自らの意志で変革に踏み出すべき瞬間を迎えている。
小泉進次郎の起用は、その第一歩に過ぎない。だが、それは“単なる一歩”ではない。目覚まし時計はすでに鳴っている。日本は眠ったままでいられるほど、世界は甘くないのだ。
文:林直人
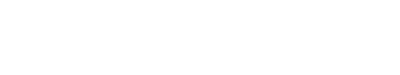
-1-697x1024.jpg)
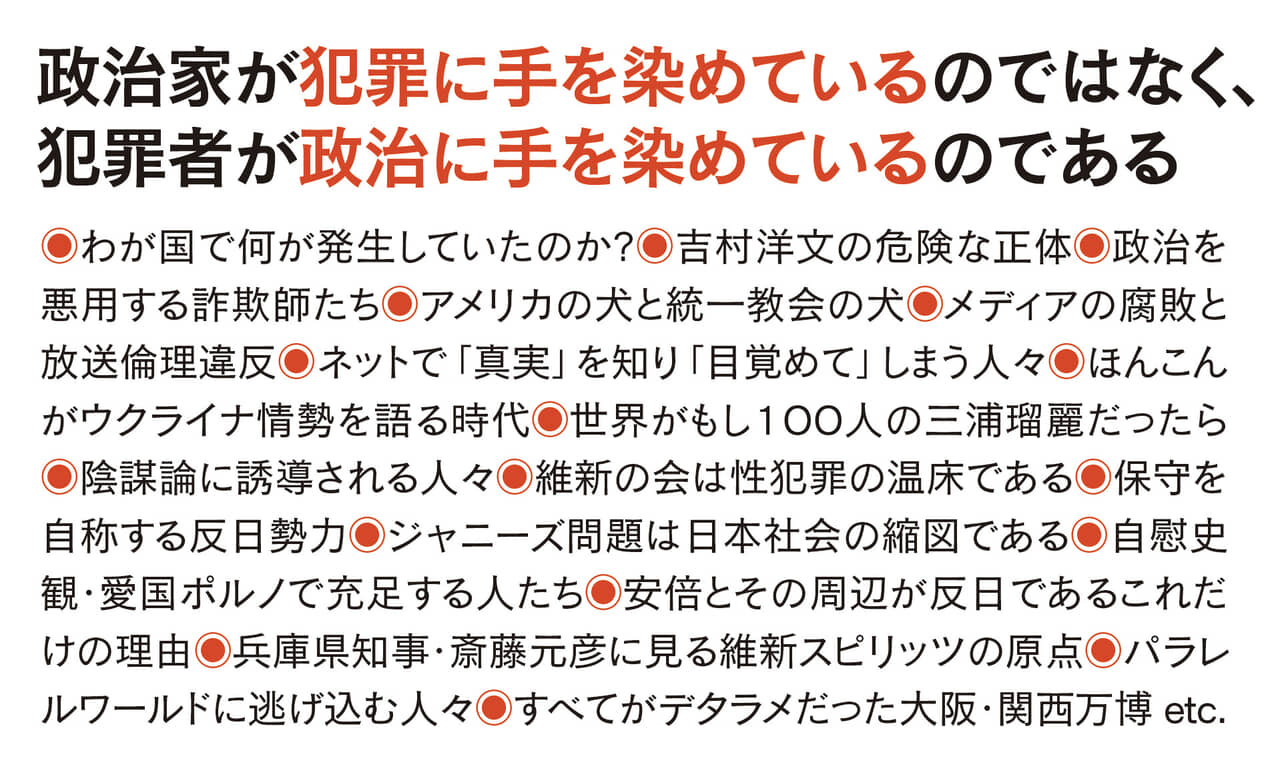
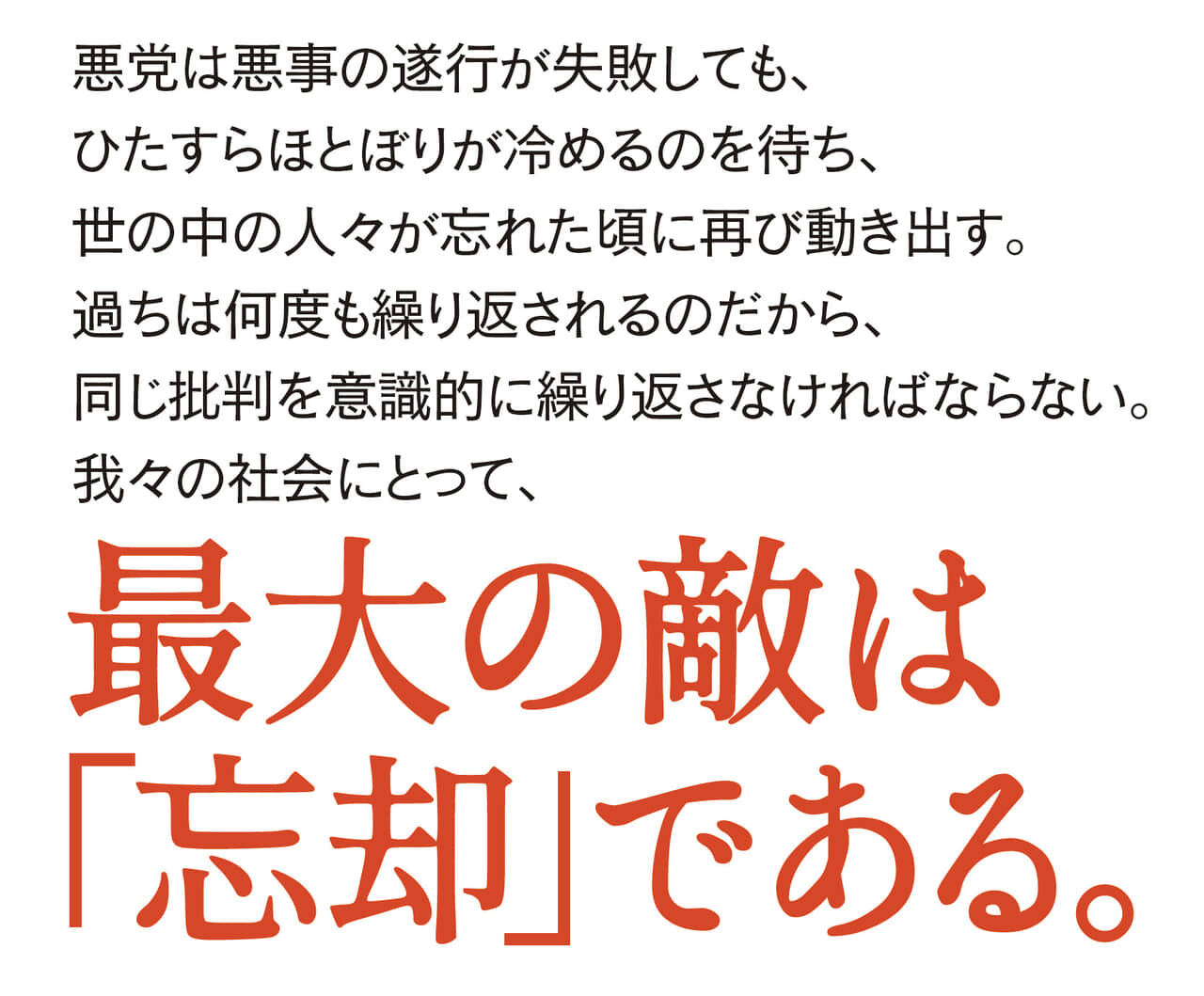
-697x1024.jpg)