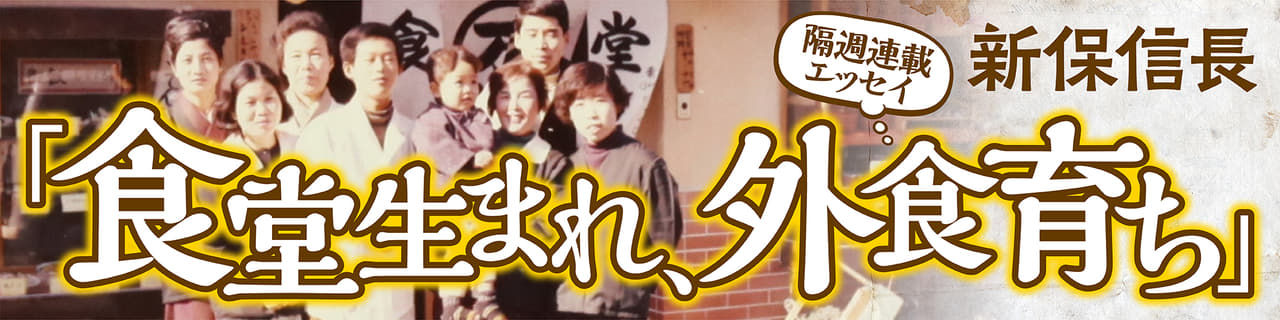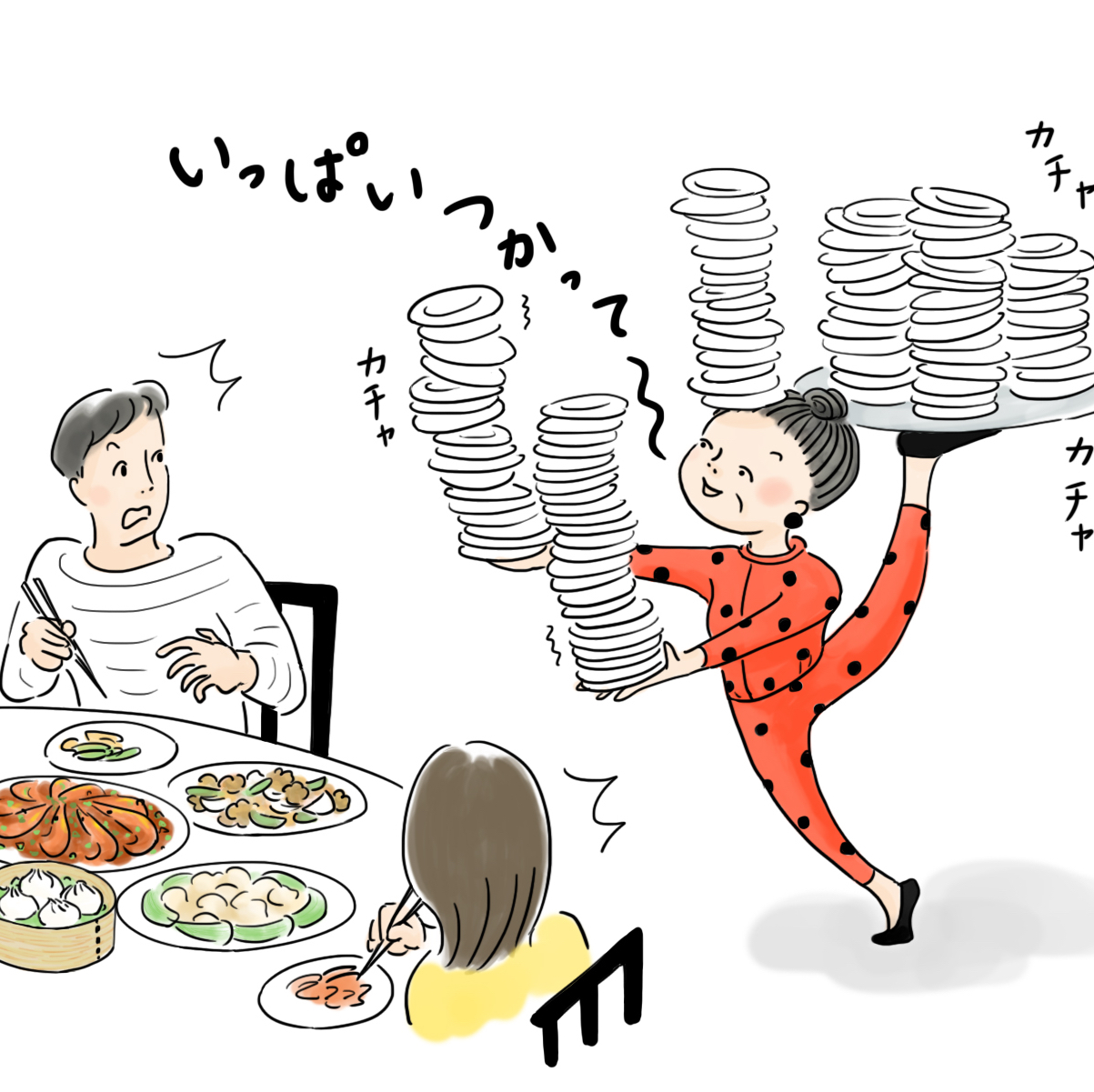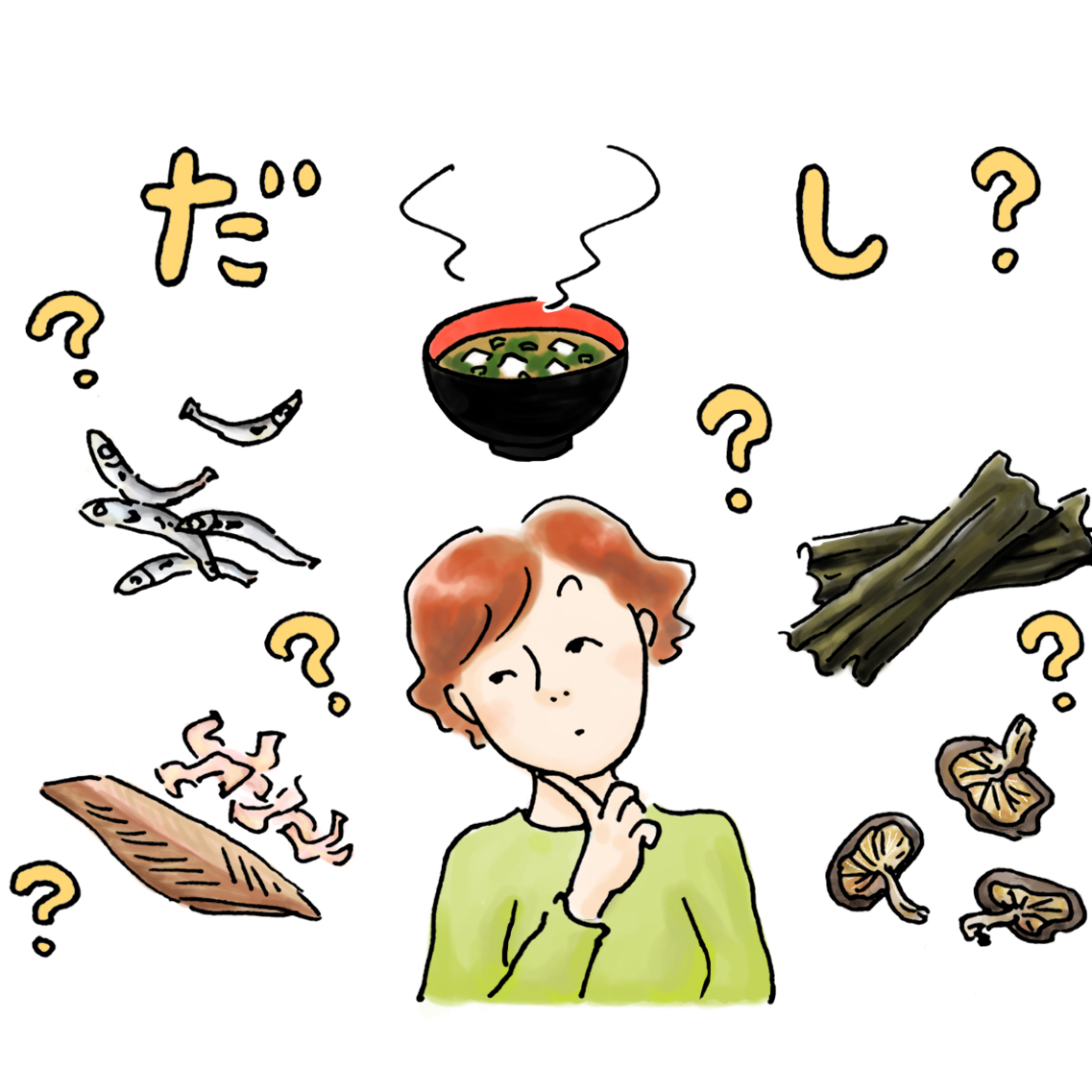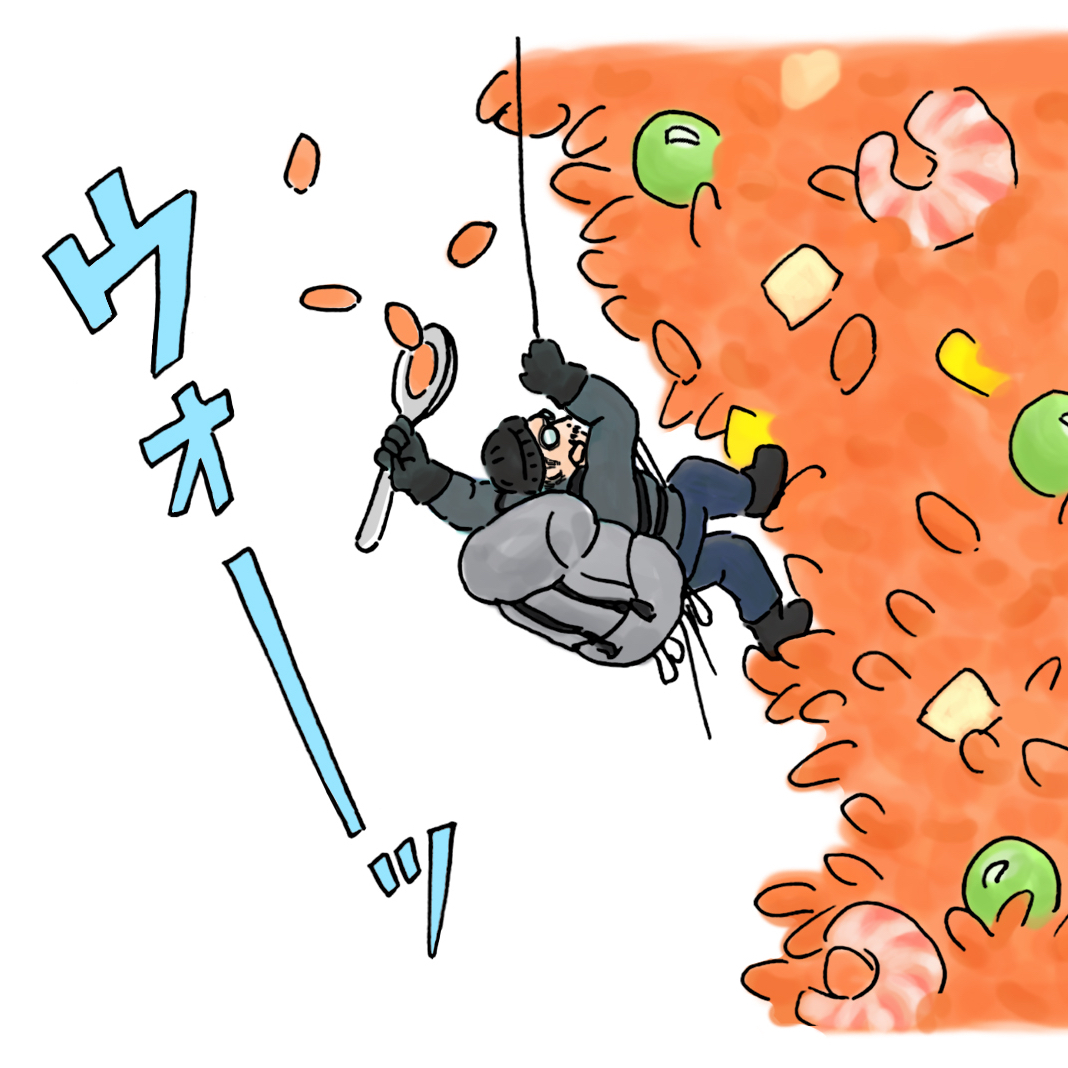新保信長『食堂生まれ、外食育ち』【16品目】最高のおやつ
【隔週連載】新保信長「食堂生まれ、外食育ち」16品目
「食堂生まれ、外食育ち」の編集者・新保信長さんが、外食にまつわるアレコレを綴っていく好評の連載エッセイ。ただし、いわゆるグルメエッセイとは違って「味には基本的に言及しない」というのがミソ。外食ならではの出来事や人間模様について、実家の食堂の思い出も含めて語られるささやかなドラマの数々。いつかあの時の〝外食〟の時空間へーー。それでは【16品目】「最高のおやつ」をご賞味あれ!

【16品目】最高のおやつ
我が家には「おやつ」のシステムがなかった。マンガやアニメの描写、カステラの文明堂のCMなどから「3時のおやつ」というものが世の中に存在することは知っていたが、子供の頃に「おやつですよ」と何かを出されたことはない。友達の家に遊びに行くと、その家のお母さんがお菓子を出してくれたりして驚いた。市販品ではなく手作りの焼き菓子みたいなものが出てくると、「え、なんでわざわざ?」と思うと同時に、ちょっと残念だったのも覚えている(なぜなら、手作りより市販品のほうが正直おいしかったから)。
そんなわけで、おやつ文化にはなじみが薄い私だが、だからといってまったく間食をしなかったわけではない。今はお菓子類はほとんど食べないけれど、子供の頃は人並みにお菓子好きだった。しかし、おやつとしての配給は基本的にないので、自分のお小遣いで買う。近所のタバコ屋は、菓子パンやスナック菓子、アイスなんかも売っていて、マイフェイバリットショップだった。メロンパンやジャムパンもいいが、何といっても最高峰はチョココロネ。値段もちょっと高かった気がする。スナック系は、ぼんち揚げ(関東で言う歌舞伎揚げ)かサッポロポテトかで悩む。
少し遠くの駄菓子屋には、友達と自転車で行く。カレー風味のスナックやラムネ、噛んでるうちに溶けてなくなるガム、得体の知れないゼリーなど、100円あればそれなりにいろんなものが買えた。くじを引いてハズレのときにもらえるコイン型のチョコも好きだった(なんか粉っぽい味。包装紙なしのむき出しで渡される)。
ただし、お中元やお歳暮の季節になると話は別だ。もらいもののお菓子(缶に入ったクッキーとか)が居間に置いてあって、勝手に食べていいことになっていた。それでも一瞬で食べ尽くすようなことはせず、「一日いくつ」と決めて計画的に食べていたのは性格だろう。お中元でもらう水ようかんとプリンの缶詰セットは夏のお楽しみ。これも一日1缶だ。
両親の出身地である石川県の銘菓「柴舟」も年一ぐらいで届いた。生姜糖風味の煎餅は子供の舌には合わなかったが、ほかに食べるものがなければ食う。同じく石川県の名産でクルミの佃煮もあった。ゴリ(ハゼ類の小さな川魚)の佃煮などとセットで送られてきて、ゴリは朝ごはんのおかずや父の晩酌のアテになるものの、クルミはあまり消費する場面がない。残ったものをおやつ代わりに食べてたら、母の脳には私の好物としてインプットされたらしく、いまだに正月などに「これ好きやろ」と勧めてくるのが困りものだ。
それ以外にも、果物が置いてあることは結構あった。みかんやバナナは子供でも簡単に皮を剥けるが、問題はリンゴや梨である。両親とも店に出ているので、剥いてくれる人はいない。リンゴは皮ごと食べてもいいが梨はちょっとつらい。となると、自分で剥くしかない。住居スペースに台所はなかったが、包丁は1本置いてあった。サイズ的にはペティナイフぐらいのやつ。もともと手先は器用なほうなので、すぐに皮剥きはマスターした。リンゴ丸ごとを途切れさせずに剥くこともできる。自分で料理をするようになったのはコロナ以降だが、そのとき覚えた包丁の扱いは大いに役立っている。
- 1
- 2