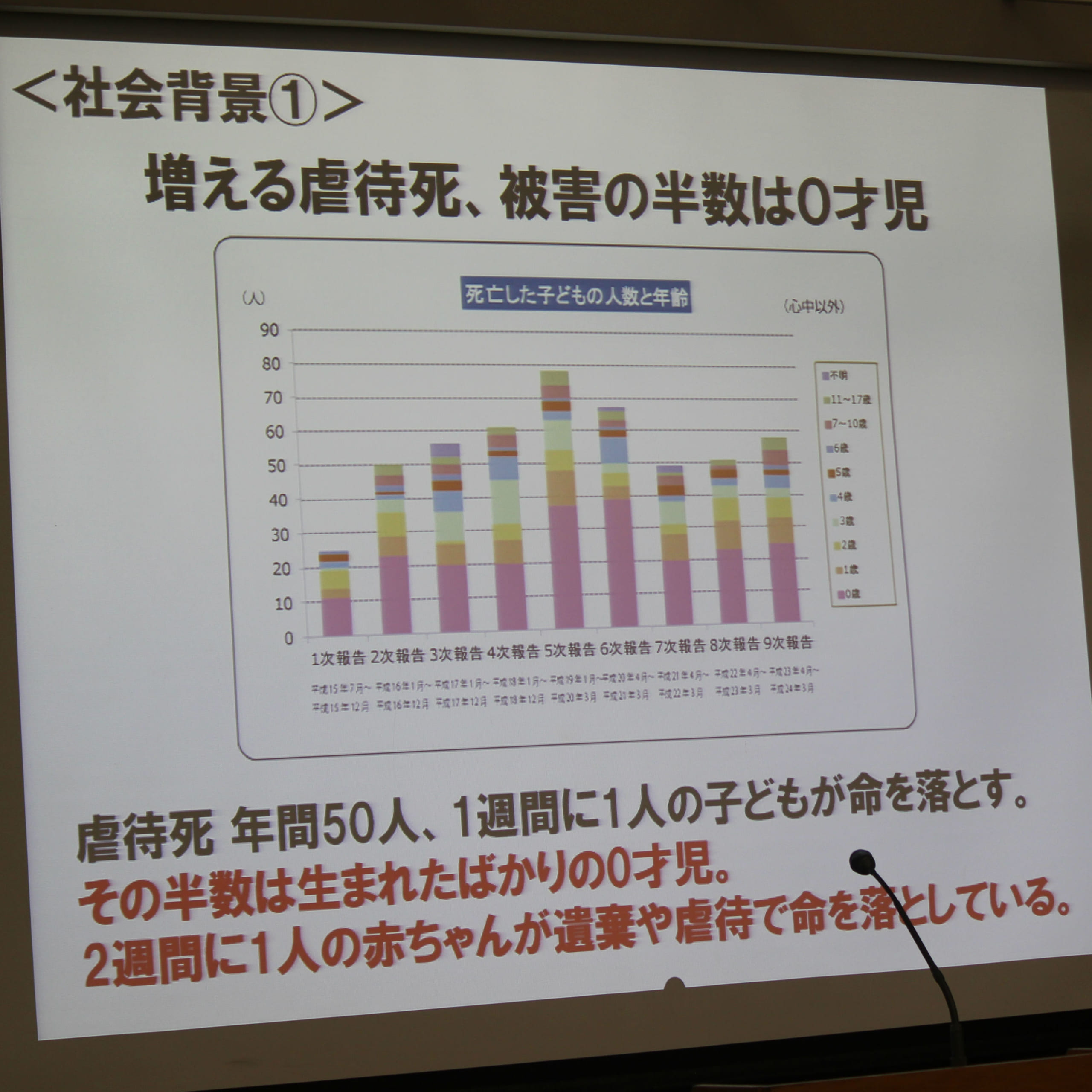「名古屋」と言えば金の鯱。その起源
名古屋の「鯱」の謎を解く 真実の名古屋論⑤
いままた名古屋ネタのテレビ番組や書籍が流行し、「名古屋ブーム」が再燃している。そしてその中にはなんの根拠もないのに語られるトンデモ名古屋論が存在する。しかもそれら言説は「名古屋イジメ」のようなあまりに酷いものが多いという。そのことを指摘した書『真実の名古屋論〜トンデモ名古屋論を撃つ』が話題だ。名古屋といえば「金の鯱(しゃちほこ)」が有名であるが、その起源を知る者は少ない。今回、その著者呉智英氏が「鯱」の謎について語った。
カタカナで「シャチ」ではない!
「鯱」の魅力
井上章一は「シャチ」と片仮名で表記するが、私は漢字で「鯱」とする。動物名をむやみに片仮名表記する風潮が好きではないからである。とはいうものの、鯱は動物なのか。哺乳類なのか、魚類なのか。そもそも、実在するのか。そして、鯱鉾の起原はどこに求められるのか。このあたりの追究が、この本の読みどころである。

名古屋城は1945年5月、終戦を目前にして米軍の空襲によって炎上した。この名古屋城の天守閣の屋根には一対の金の鯱鉾が輝いていた。城や寺など建築物の屋根に鯱鉾を置くことは全国的に珍しいことではない。特に西日本では一般の民家でも鬼瓦のような魔除け、火伏せのまじないとして鯱鉾を置く風習がある。東海道山陽新幹線が広島県東部の三原にさしかかると、車窓から見える民家の屋根の多くに鯱鉾があるのが分かる。ただ、豪華な金の鯱鉾は徳川御三家の一つ尾張の名古屋城にしかない。金の鯱鉾は尾張名古屋の象徴であった。戦後の混乱が収まり、一九五九年に名古屋城が再建された時にも、当然、金の鯱鉾も屋根の上に燦然と輝くことになった。
こうした歴史的経緯があり、名古屋ではあちこちに鯱が町のシンボルとして図像化されている。

ここまでは、名古屋人のみならず、広く知られている。しかし『名古屋と金シャチ』では、そんな常識をなぞったりはしない。それをここで全部紹介している余裕はないが、私にはその起原を世界中に探すところが面白かった。直接的に系統づけられるかどうかはともかく、鯱鉾と同じ形の絵、彫刻、塑像が世界各地に観察できるのである。一番驚いたのが、ギリシャ、ローマなどの神話的海獣が鯱鉾によく似ているという指摘である。