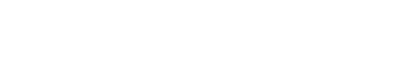新選組はなぜ作られた?
新選組結成の秘話 第1回

荒廃する京へ将軍が200年以上ぶりに上ることになった。時の将軍家茂を警護するため、幕府は江戸で浪士組を募集。これを聞いた近藤、土方、沖田らが集まり、最強の剣客集団が誕生することになる!
黒船来航から激動した幕末
新選組誕生の背景を探る!
3代将軍徳川家光の治世だった寛永18年(1641)に、長崎出島にオランダ商館を設置したことで、日本の鎖国は完結したとされる。だが、時とともに、接近する外国船は数を増した。文政8年(1825)には、異国船打払令が発令されるに至った。
弘化3年(1846)通商を求める米国艦隊が浦賀に来航するが、日本はこれを拒否、そして嘉永6年(1853)、再び米国艦隊が浦賀に来航した。艦隊を率いる司令長官ペリーは、通商や薪水の供給を求める大統領の国書を持参していた。
独断で江戸湾の測量まで開始したペリーの姿勢を畏れた幕府は国書を受理、翌年、日米和親条約が結ばれた。
国内は沸騰していた。長い鎖国状態を打ち破られ、攘夷の声が巻き起こる。町の武術道場は、異国人と対峙しようとする者たちで活気づいた。江戸市ヶ谷甲良屋敷にあった天然理心流撃剣道場の試衛館では、来客に沢庵を振る舞い、これを「メリケンの刺身」と呼んだという(『近世剣客伝』本山荻舟)。異国人を刺身のように切り刻んでやるという勇猛な信念で、後に道場主となる若き日の近藤勇は、腕を磨いていったのだろう。
やがて大老職に就いていた井伊直弼は、安政5年(1858)に、米国との通商修好条約の締結を断行する。当初から朝廷は締結を拒絶しており、勅許も得られぬ中での調印だった。オランダ、英国、ロシア、フランスとも次々に修好通商条約は締結された。
さらに井伊は、当時国論を二分していた13代将軍徳川家定の後継者問題を専断し、14代将軍として紀州藩主の慶福(家茂)を定めた。一橋家の慶喜を押していた水戸藩主の徳川斉昭や福井藩主の松平春嶽ら諸侯を強引に隠居させ、政治の表舞台から除いた。さらに、井伊を排斥する活動を進める橋本左内や吉田松陰らを処断した。
こうした専断姿勢は怨憎の的となり、安政7年3月3日、井伊は登城中に桜田門外で水戸藩の活動家らに暗殺される。
予期せぬ事態に権威の失墜を畏れる幕府は、公武合体を推進した。14代将軍となった家茂の御台として、文久2年(1862)2月、孝明天皇の実妹である和宮を降嫁させた。婚儀は公武一和のなによりの証となるはずであり、あわせて幕府は朝廷に、遠くない時期に攘夷を行なうことを約束していた。
だが、過激な攘夷派の活動は収まらなかった。諸外国との条約廃棄を求める者たちの中には、江戸の公使館を襲撃するなどの実力行動に出る者もいた。
切迫する事態を打開するため、将軍家茂の上洛が検討され始めていた。家茂の上洛は5月26日に内定するが、根回しに動いた松平春嶽は自著の『逸事史補』に、問題は「大に沸騰を生ぜり」とし「ぜひ上洛すべき事当然たりという者十の九に居せり」という状況だったとしている。
攘夷への軸足が定まらない幕府にとって、家茂の上洛と朝廷への接触は、多くの危機を伴うものだった。だが、国難を打開する目的での公武合体を推進するため、この上なく意義のあるものだった。
京都でも将軍の上洛は望まれていた。
6月には大原重徳が勅使として下向し、上洛の要請や、人事の提案などを行なっている。帰途、随行していた薩摩藩主島津久光に帯同した薩摩藩士が、神奈川宿の生麦で、行列を横切った英国人を無礼打ちにしている。この問題での英国側の対応が、翌年春の新選組結成へのひとつの端緒となっていく。
さらに11月からは三条実美らが勅使となり、攘夷の実行などに関する諸件を具申した。12月5日、家茂は彼らに「上京の上、委細申し上げ奉り候」と答えている。家茂の上洛は既成事実として公言されたのである。
将軍の上洛は3代家光以降、200年以上も行なわれていなかった。この文久2年、京都では頻繁に市街での暗殺や梟首が行なわれており、治安面での問題が提起されていた。年末に発動した京都守護職による治安維持活動も、緊急的なものである。
近藤勇は後に京都で「惜しからぬ命一つを二つ三つ四つも欲しきは君がためかは」という和歌を詠んだ。「君」とは天皇を指すと同時に、将軍をも指していたに違いない。
激動の政局が、彼らを京都に誘い、大切な「君」を2代にわたって衛らせることになっていく。